- 恐怖の館
-
嵐の夜、森の中で道に迷ったあなたは、不気味な洋館にたどり着いた……。
暖炉のある部屋を探し出し、いの一番に部屋に火をつけたのちに、窓を割って脱出する。
炎上する館。どうしてこんなことになってしまったのか。
こうして惨劇の夜は幕を閉じた。
ミナコ「うおおおおおお重い。重い。ねえ重いよ? つらいよつらいよ?」
サトシ「終業式までに教科書とか全部持って帰らないといけないからな。でもオレは重くない」
ミナコ「そろそろ自分で持ってよ」
サトシ「次の電柱までだ。ルールだろ」
ミナコ「電柱ぜんぜん見えないじゃん。鬼!? ってゆーかもうそこサトシんちだし!」
サトシ「だから次の電柱までがルールだ。持ってろよ」
ミナコ「いや家に着いたら帰るよねサトシ」
サトシ「帰らない。ルールだ」
ミナコ「あんたは電柱まで歩く必要ないじゃん」
サトシ「ルールだ。お前と電柱まで行って、それから荷物を返してもらって引き返す」
ミナコ「……あんた、あたしと一緒にいたいだけでしょ」
サトシ「そうだよ。だから何?」
ミナコ「うお開き直りかよ」
サトシ「開き直りってのは悪事に使う言葉だろ。なあ、オレがお前を好きだと悪なの? 何がどう悪いの?」
ミナコ「うあこいつ……屁理屈に告白を紛れ込ませるかよ」
サトシ「どうしたミナコ。顔赤いよ。オレがお前を好きだと言った途端突然に。具合悪いの? なあ具合悪いのか? だが荷物は持てよ」
ミナコ「クソ重いしムカつくしなんか恥ずかしいし……なんか今あたし最高に気分が悪いんですけど」
サトシ「だろうな。でもオレの気分は悪くない。特に好きな奴と一緒にいられるあたりがなあああああああ!」
ミナコ「……ぶっ殺す」
サトシ「は。そういうのは相手の目を見て言えよ。顔赤くせずにな」
ミナコ「ぶっ殺す!」
サトシ「声でけえよ。顔赤ぇよ」
*「いいえあなたは狂ってはいません。これはあなたの夢です。夢なのですから、理に外れることも起こりましょう。そしてわたしは蜘蛛の総意です。あなたに救済のつもりはなかったでしょうが、あなたが益虫と広めてくれたお陰で、わたしたちの多くが淘汰を特別に免れているのです。そのお礼だけをいかにしても申し上げたく、こうして奇跡に頼っている次第です」
あなたは恐縮して「これはこれはご丁寧に」と、障子にとまった、指先ほどもない小さな蜘蛛に頭を下げた。

それは長い物語だった。
かれは強かった。幼い頃から既に人並み外れていた。
そのうえ純粋だった。と言っても、現実の闇に触れてたやすく折れてしまうような脆弱なものではない。どれだけ泥をかぶっても汚れない本当の純粋だ。かれは腕力だけでなく、心も強かった。多少の痛みはものともしないし、他者にも優しかった。
初めからすべてを備えていたと言ってもいい。論理思考や抽象思考には劣るところがあったが、それはかれには必要ないものであり、かれの無欠さを少しも損なうものではなかった。なぜならかれはただ、戦えれば良かったからだ。そのために必要な力も、好敵手にも、不足することは生涯なかった。
その上でかれは成長していった。多くを獲得していった。際限なく大きくなっていき、しかもその制御を失わなかった。力に振り回されなかった。自滅しなかった。
かれは戦いと冒険を通じて多くの友を得た。伴侶も子供も得た。
しかもかれは失わなかった。どんな者でも最後には老いて朽ちてゆくしかないはずなのに、かれはそうならなかった。
かれは老いに強かった。
かれは病に強かった。
かれは死に強かった。
かれは距離に強かった。
かれは時間に強かった。
あらゆる環境、あらゆる災い、あらゆる現実的制約もかれを害することだけは出来なかった。
そう、かれはすべてに強かった。
その物語もいつしか幕を閉じた。
そして今もその不条理とさえ言える強さとともに、かれは語り継がれている。
読み終えた女も本を閉じた。明かりを消し、目を閉じて、愛おしむようにつぶやく。
「界王拳、五十倍」
ゆるく握った手の内側に光が灯ったのは、感受性豊かな彼女の主観だ。しかしその静かな光は、唱えた言葉の意味する分だけ明るくなる。
彼女は信じている。優しく万能なかれは虚実の境をも越えて、彼女に力を与えてくれるだろう。
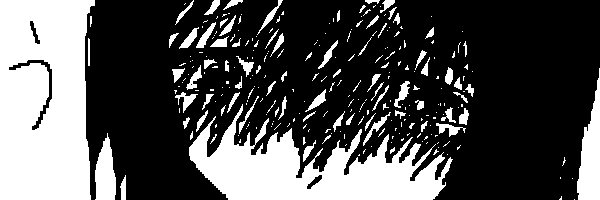
う。
彼女は自分の本質が「う」そのものなのだと執拗に繰り返す。それ以外に他人にアピールするものが無いからだ。だから友達と昼に食べるものを決める時でも、うどんやうなぎといったうのつく選択肢が視界内にあれば、必ずそこにしようと訴えた。居酒屋で卯の花が通しに出れば、周りに懇願してそれを独り占めにした。友達から「う子はホントにうの鬼だよね」と言われることで彼女は他者との繋がりを確認し、自我の安定を得ていた。周りの人間も彼女のうっぷりに突っ込みを入れれば安定したコミュニケーションが取れるので、彼女のウピールに付き合った。
いでもえでもなくうなのはただのランダムだ。うであることに意味は無い。だが強いて言えばその音感だろうか。いくらランダムでも「げ子」などと名乗ったりはしなかったろう。あ行の発音の簡単さが醸し出す幼児性とう段の発音の身を縮こめるような内向性を、自分の飾りとして好ましいと無意識のうちに思っていたのかも知れない。それは多分に小動物的で、小柄な彼女に似合っていた。
しかし彼女はやり過ぎた。自分が注目されていないと感じると、特に何も無い時でも「うー!」と唸って反応をせがんだ。会ったばかりの人間の中には顔をしかめる者もいた。見知った仲の友人でさえ、エスカレートしてゆく彼女のウピールを次第に疎ましく感じるようになった。
「あいついい加減にして欲しいんだけど」「ねー。う子はまじでうだよね」
陰で「う」は「うざい」を意味する隠語になった。これによってう子は公然と「う子ってほんとう過ぎるよね」と罵倒されるようになった。う子が「う」と発音するのに合わせて、他のものが「ざ」と繋げる遊びも発生した。
う子は自分の置かれている立場に薄々気付いていた。だが簡単には引き返せなかった。バケツ一杯にうどんを盛られたときも、歓喜して見せてそれにとりかかった。しかし三分の一ほど食べて止まった。限界だった。大好きなんでしょほらもっとどんどん食べなよ。あれなんで泣いてるの? 嬉し泣きだと彼女は答えた。「う」れし泣きかそうかあ。「う」ん、「う」れし泣きなの。あはははは。わはははは。で、まだ食べてくれないの? 全部う子のために用意したんだから遠慮しなくていいんだよ。
う子は吐いた。胃からうどんが競り上がってきたとき、小さな口が目一杯開いた。「あ……」 しかしすんでの所でその開き具合を抑えた。うどんを吐くのは止められなかったが、呻き声は寸での所で制御した。「ぁううううううううう」 友達と思っていた人間の悪意で嘔吐の醜態を強いられた彼女に残った、それは最後の矜持だった。「うううううううえうえう」 うどんの残骸を温泉のライオンのように垂れ流しながら、彼女は思った。そうだ。「う」だ。自分は「う」の子なんだ。
吐いた後に彼女は、ひとりごちた。それは世界に向けての自己紹介だった。神がいたなら聞き届けていただろう。彼女はその無意味な執着を、誰の得にもならない拘りを、墓場まで連れてゆくつもりだった。その一文字に彼女のすべてが圧縮されていた。
う。
- メダル
-
夢の中で僕は旅人だった
何か知らないけど流浪の旅をしてた
途中で立ち寄った町の酒場でなんか騒動を起こした
なんか分からないけどそれがその国ではすっごいまずい行為ですっごい悪い罪で、
ぼくは最悪の地獄のような強制労働場に捕らえられた
一生ゲリ以下の扱いで暮らすことが確定した
脱獄した
そこで知り合った仲間と三人で共謀して脱獄だ
脱獄なんて見つかったらもうすげえ有り得ないくらい地獄の罰を受けるんだけど、
スゲエいろんなトラップを狡猾にかいくぐりかいくぐり、
ぼくらは娑婆の間近まできた
ところが最後の塀を超える最後の最後の直前でどうしようもない難関にぶち当たった
囚人カードを持った上で、三つのカメラの認証をパスしないとレーザーで焼き殺されるゲートだ
囚人カードをぼくらは一枚ずつ持っていた
カードを捨ててはならない
囚人カードを持った人間がそのカメラの認証をパスするには、三つのカメラそれぞれが記憶してるぼくらの情報である、正面写真、横写真、顔写真、と、カメラに映るぼくらの姿が一致しないように、
かなりアクロバティックな動きでゲートを通過しないと無理だった
喩えるなら、歩道橋からきりもみ二回転半しながら飛び降りて、下を走るバイクの頭に手をついて逆立ちで着地するようなもんだ
できるかそんなもん
不可能確定
仲間のうちデブが別の仲間の囚人カードをぶん取った
べつに、他の人間の囚人カードを持っても全く得は無い 認証はパスしやすくはならない
囚人カードを取られた仲間はいきなりだったので、なんでカードを取られたのか分からなかった
そしてデブはぼくにも、カードを渡せ、手を出してきた
ぼくはそいつがこれから何をやろうとしてるのか分かっていたのだが、その上でカードを渡した
「キャラ的によ、オレがこうするぐらいしかしょうがないだろ」
そんなことを言って、デブはカード三枚を持ってゲートにきりもみ回転しながら飛び出した
アクロバットは当然失敗して、デブはレーザーで瞬殺された
囚人カードはデブごとレーザーで焼き殺され、ぼくらを囚人と記憶する情報はこの世から失われた
ぼくらはゲートを通過できるようになった
残った仲間がぼくを憎悪の目で睨んだ
「なんで渡したんだ お前あいつが何するか分かったてたんだろ なんで渡したんだよ!」
そう言ってぼくの元から去った
もっともな言い分だった
ぼくは自由の身になったが、友達を二人失った
ゲートの先は酒場に通じていた
人がいっぱいいて、誰もぼくが罪人だとは分からない
と思ったら ぼくは青い帯を持っていた 紛うことなき囚人の証である、あの忌まわしき青い帯を
ぼくはヤベエと思って、一刻も早くこの場から去ってこの帯を処分しなければ、と
帯が他の人間に見つからないよう無理やり握り締めて、酒場をそそくさと出ようとした
オカマのマスターに呼び止められた
「ちょっとあんた待ちなさいよ」
「待てない、喋りかけるな」
「いいから、困ることじゃないでしょ」
「うるっせえな、この世にはお前の想像できないすげえいろんな特殊事情があるんだよクソ垂れて死んで死ねよ」
「分かってるわよ 困ってるんでしょ」
そう言ったオカマは、事情を聞かないまま、どこに逃げればいいかを教えてくれた
オカマもこちらから見れば常識の世界の人間だから、青い帯を見れば速攻でこっちをゴミ扱いしてすぐ通報するのが確定のくせに、何も知らぬまま 親切にぼくを助けた
ぼくは急いでオカマの言った方向へ逃げて行った
青い帯はいつの間にか処分した
これで自由確定 真人間
ぼくは砂漠を強行して別の町を目指した
別の町に着いたが、そこはバグでデータが失われた町だった
町が近づいてもほとんど大きくならず、ミニチュアのままで画面が切り替わりもしない
しょうがないのでミニチュアの簡略化された町表示を通過してさらに進んだ
それとはまた別の町に着いた
腹をすかせたぼくはバザーみたいなフードコートみたいなところでカップアイスを買った
そこでばったりと、高校のときに昔別れた友達と出くわした
そいつはゲートの件とは違う奴だが、高校のときにぼくを許せなくて僕との関係を切った奴だった
ぼくはそいつのことをずっと気にしてた
お互い あ って顔になった
そいつは同じカップのアイスを食べていた
ぼくはそいつの食べかけのカップアイスに自分のを未開封のを当てて
「一緒に食わねえか」というジェスチャーをしようとしたが、かわされた
今でもぼくを許せないのだろう
ぼくはあきらめて一人で食べることにした
フードコートみたいな人がいっぱいいる座席に空きを見つけて、一人さみしくアイスを食べた
そしたら後ろからそいつから斬りかかられた
やべえって思ってぼくはそいつの斬撃を防いだ上で反撃した
二度と斬りかかられることのないよう、殺してはないものの、フォークを目玉にブッ指すくらいのなんか酷い反撃をした
そして逃げた
逃げた先のどっか(なんかの二階みたいな畳のところ)でメシを食ってたらそいつがまた襲ってきた
「お前は最低の奴なのに全部持ってる、妬ましい、ふざけんな」的なことを言って襲ってきた
ぼくはふざけんなと思ってそいつと取っ組み合ってやり合って押し倒した
埒が明かないしもうぶっ殺すかと思ったとき、ぼくの携帯でチャリーンと音がした
画面を見たら、メダルをはめる穴のある画面になっていて、メダルが12枚も嵌っていた
そのメダルを見るや否や、そいつはすげえ驚いていてぼくに怒るどころじゃなくなっていた
そうだよ
そのメダルは、1枚1枚が、それが一枚あるだけでこの世の何にも勝る価値を持ち、売ればすげえ金になるのは勿論のこと、たとえ百万人殺してようがその罪がすべて贖われ、すべての疑問の答えを得て、この世のあらゆる富や賞賛を浴び、道徳的にも最高の善を為したのと同等の意味を持つ素晴らしいすげえメダルだった
それだけで人生の意味がすべて獲得でき、もういつ死んでも大丈夫なくらいの、精神的にも物質的にも磐石のすべてを得られる最強のすごいメダルだ
一枚だけでもそんな凄いものを、それをぼくは何の条件を満たしたのか、12枚も獲得していたのだ
ぼくはそれで糸が切れて、これ以上ないほど激昂して喚いていた
「なにが全部持ってるだ、ふざけんな、なんにもねえし酷い目にいっぱい合ってきたよ、お前みたいなゲリに分かってたまるかよ、おれはなあ、これくらい貰えて当然なんだよ、これくらいの役得がねえとやってられねえよ、そのくらいの人生歩んできたんだよ、ほんと、ほんとにこんなのが無きゃやってられねえよ、ふざけんなよ、ほんとふざけんなよ、やってらんねえよ、何なんだよいい加減にしろよ、なんでこんな目にばっかり合ってこなきゃいけないんだよ、ほんともうなんなんだよ誰か教えろよふざけんなよ」
激昂と感情の吐露に浸りながら、ぼくは頭になんか迸らせて、号泣しながらそんなことを喚きまくっていた
涙がほんともう滝のようにぼろぼろ出た 出まくった
ゴールだ
もうすべての結論が出て、
はっきりしたゴールに到達したところで、必然的に目が覚めた
そのままぼろっぼろ涙が出てた
枕とか濡れた
涙が出るのに任せながら、ぼくは、すげえ夢をみた、すげえ夢をみた、と思っていた
メダル……
- 一日一小説大会2
-
ノベラゴン。
2009/08/23(日)〜2009/08/29(土)の一週間、小説を一日一個ずつ書いて発表します。
分量は6KB(=6144Byte)(=全角3072文字)以上。
便乗する人は自ブログなり自サイトなりのURLを掲示板にどうぞお貼りください。期間や分量は適当にセルフカスタマイズしたらいいと思います。
じすさんもやります。
- 一日一小説大会、僕の
-
- [04/07] ドードリーのファンタジー [7136Byte]
- [04/08] パラメータ合計10のファンタジー [6596Byte]
- [04/09] ニワトリアス [10767Byte]
- [04/10] ファンタジー学園 [7061Byte]
- [04/11] 病 [6144Byte]
- [04/12] アンディーメンテ行きレインボートレイン [10259Byte]
- [04/13] 我が名はインターネット [10006Byte]
- 一日一小説大会
-
ノベリアス。
2009/04/07〜2009/04/13の一週間、小説を一日一個ずつ書いて発表します言っちまったよもう降りられない。分量は6KB以上。
にぎやかな方が楽しいでしょうから、便乗してやろうかという人がいたら、自ブログなり自サイトなりのURLを掲示板にペッタペタどうぞ。期間や分量は適当にセルフカスタマイズしたらいいと思います。
じすさんもやります。
- 補足 [04/06]
-
1KBは1024Byteとします。なのでデフォルトのボーダーは6144Byteとなります。
龍の帝国があった。彼らは巨大な体躯に加えて膨大な知識と知恵を持っていた。しかし物を作るための器用な手先は無かったので、その知識の記録と再生のために、人間を国ごと囲って工芸奴隷として使役していた。そのうちのひとつである書記奴隷は龍が発する言語の音をそのまま記録し、あるいは記録をそのまま読み上げる。龍たちは情報の記録のために人間と話すときとは異なる言語を作成し、なおかつ定期的にパターンを変えながら暗号化してから発音していたので、書記たちがその内容を解析することは出来なかった。
ルルフスは龍の末裔の雄であったが、龍としては極度の変態的な性嗜好の持ち主で、書記奴隷の娘に恋をしてしまった。恋されたのはシニカという名の、とても聡明な少女だった。彼らは他の龍と人間たちに隠れて時々密会し、触れ合った。シニカはルルフスとの戯れの中で≪龍脈≫の暗号パターンを教わり、さらには頼み込んで≪龍脈≫の閲覧の機会を得た。龍たちの記録は言語学・数学・科学・魔法の秘儀・宗教・芸術など、多岐に渡った豊かなものだった。思春期の期間にそれらを読み耽ったシニカはそこで得た知識を組み合わせて、龍の殺し方を考えた。ダイヤモンドでガラスを切る方法からの着想で、頑健な龍の細胞を傷つけるために、龍自身の鱗を利用することを考えた。ルルフスをそそのかして鱗を得て、繊維に沿って削り出して剣を作った。その剣で試しに木の幹を斬り付けたところ、まるで草でも薙いだかのように抵抗なく切断することができたため、≪草薙≫と名づけた。
シニカは適当に勇者を探し、≪草薙≫を与え、一匹で眠っていた龍を攻撃させてみた。龍は死んだ。シニカは技術者としての満足感を得た。だがその先のことを考えるのを忘れていた。巨大な死体を隠す暇も処分する暇も無いままに、事件は龍たちに発覚し、ルルフスは馬鹿をしでかした罰で檻に閉じ込められ、自分の行いを激しく悔いた。龍を殺した勇者も龍たちに捕らえられて惨殺され、≪草薙≫は破壊された。たが、シニカは姿をくらましていた。
何者かによる龍たちの斬死事件が相次いだ。それは龍に隠れてクーデターチームを組織したシニカたちによる、量産した≪草薙≫の運用テストだった。さらにシニカたちはルルフスを捕らえる檻を破壊し、ルルフスを解放した。チームのメンバーはどこからともなく現れて龍を殺しては消え、そのアジトを龍たちが補足することはできなかった。
龍たちはシニカたちに対抗するために、実験的に作成されていた龍人を使うことにした。龍人は龍の強さと人間サイズの肉体、器用さを兼ね備えており、シニカたちを始末するためのエージェントとして育てられた。奇形や精神障害の多い龍人たちの中で、刺客として機能しそうなのは4人だけだった。龍人たちはクーデターチームを追った。
龍人たちはアジトをつきとめて襲撃した。龍人たちの俊敏な挙動の前には強い剣もあまり役に立たず、クーデターチームは半壊した。シニカたち数名はアジトから脱走したが、追われた龍人たちに追い詰められた。すんでのところでルルフスが駆けつけ、龍人たちと戦ったが、龍人たちの装備した≪草薙≫で殺された。龍人たちも二人死んで残り二人になった。シニカはその間に逃げおおせた。
シニカはルルフスの子を産んだ。堕胎しなかったのは、龍人たちとの戦いのなかで、龍人こそが龍も人も殺せる最高傑作になると気づいたからだ。出産のショックでシニカは死に、生まれた子供はクーデターチームによって、龍殺しの希望として育てられた。
クラス内ヒエラルキーでの下克上は望めなかったから、理想を虚構に彼女は求めた。灰色の日常とは乖離した、精神の幸福を保障する高次の概念を彼女は求めた。
論理7、直感3の割合で彼女は思考の海を泳ぐ。
それは前人未到の新雪であってほしかったから、それは既存の物語や神話、偶像の模倣であってはならなかった。
それは美しく色鮮やかでなければならなかったし、それは地上から手が届かないほど高くに在らなければならなかった。
それは茫洋とした巨大さを湛えていなくてはならなかったし、それはしかし同時に念頭に留めるに足る具体的なビジョンを持っていなければならなかった。
オーロラ。
消去法で絞り込んだ解がそれだった。彼女はテストの空き時間に目を閉じて、それのことを思ってみた。ビジョンは胸の中に広がり、得も言えぬ充足感を彼女に与えた。その感覚は、彼女がそれを真理として扱うのに十分な強度と持続性を持っていた。
彼女はそれが自分の求めるものの条件から導かれた、論理的な帰結であることに満足した。それを信仰することで、それを導き出した自分の知性をも間接的に自賛して愉しんだ。
彼女は人並みに成長し、人並みに本を読み、人並みに恋をして、人並みに豊かになった。その過程で素晴らしい体験や素晴らしい知識に出会ったとき、彼女は必ずそれをオーロラに結びつけた。
出会ったものの輝きを分析し、抽象化し、そうして導かれた理屈をオーロラの説明に充てる。例えばその行為を行う自分自身を、彼女はオーロラに仕える巫女として解釈した。
日常の様々な喜びや驚きは、星となって空に昇り、オーロラに編み込まれる。オーロラはより多彩な色合いを見せながら、より大きく広がっていった。
誰にも汚されたくないし、誰にも傷つけられたくないから、誰とも共有しなかった。彼女はオーロラを彼女だけの、絶対の秘密として守り続けた。その制約は、日常生活の精神活動の柱となって彼女の自我充足に寄与した。社会生活に全く支障をきたすことなく、秘密を持った女であり続けることが出来た。
彼女はやがて主婦になり、二人の子を産み、孫を抱いて、老いてそして死んでいったが、オーロラの名は墓場まで持っていった。誰に対しても、どんな時でも、口にすることは一度として無かった。
彼女は知っていた。死後は未知であることを。生者が知りえる情報では決して推し量れないものであることを。そこに待つものは、もしかしたら虚無ではないかも知れないことを。
彼女は魂となってその肉体を離れ、虹色に揺らぎながら、彼女が生まれて骨をうずめた島国を離れて、遠く遠くの大地の上空に昇っていく、その可能性に思いを馳せて、最善の末期を迎えた。
月や星の輝きは、夜が来てから鮮明になる。
「『もっと現実的なことを言え』『それは現実逃避だ』ってよ、じゃあ現実サマはそんなに偉いのかっつーハナシだよな。二点」
「そういうお前こそが何様なんだよ」
「二点って言っただろ。切り捨てたんだよ。虚空刀で。主役の俺が」
「知らねーよ」
「お前が現実役なら『うぎゃあ〜! やられたー!』ってきりもみにぶっ倒れるのがマナーだろが」
「しゃらくさいな! ええい、このテレビ(※)が目に入らぬか!」
「何だよ。バックライトついてないじゃん」
「下賤の者め、控え居ろう! ここにおわすは現実サマであるぞ!」
「はっ、これは鏡! ……そこに映るのは」
「はっは、お前が主役ってツラかよ!」
「うぎゃあ〜! やられたー!」
※ディスプレイのこと
詠唱速度だ。
それがすべてだ。そう言っても過言ではないだろう。
魔法とは何か。それは願い事の高速な現実化。定められたシステムに従って呪文を唱え、必要な効果を召喚する。衝撃を求めれば衝撃が飛ぶ。しかしそれは飛ばすだけで敵にぶち当たってくれる訳ではない。なぜなら衝撃の呪文は衝撃を飛ばす結果しかもたらさないからだ。方向を指定しなければランダムに飛ぶので、もしかしたら自分に刺さってしまうかも知れない。従って、衝撃を敵に向けて飛ばす呪文が別途必要になる。さて、それだけで相手に刺さればいいが、そこに風が吹いていたらどうか。空気抵抗に対する微修正も呪文に盛り込まねばならない。あるいはそれが街中であれば、衝撃の余波が余計なものを破壊しないように、着弾直後に消滅させる呪文が要るかも知れない。ただそのままなら大雑把な結末しかもたらさない魔法を、限りなく自分の望みに近づけるために、呪文を長くするのだ。
そして自分と同じく魔法使いの敵と対峙したなら、それはもう殺し合いだ。互いに首に手をかけあっているようなもので、どちらかの死は目前である。しかし迂闊に相手の死を望んではいけない。世の中には魔法の向きを変える魔法というものもあり、そういった安易な攻撃に対して反射のトラップとしてセットされている可能性が高いからだ。この先に何があるか、自分がどのような事象と遭遇するかを予測している魔法使いは、呪文の圧縮、自動詠唱、事前詠唱、ラピッドスペリング、隠蔽、会話偽装詠唱、効果の遅延発動、といった技術によりイニシアティブ獲得を図る。
だが現実には、事前にフォローできる事象のカバー率などたかが知れている。だから臨機応変な対応、判断力、それから地の詠唱速度が実戦ではものを言う。敵が予測できない攻撃を、敵の攻撃や防御よりも早く発動させて破滅を押し付ける。それだけで勝てる。最前線の魔法使いは常にそれだけを目指し、日々、技術を洗練させている。
闇に濡れた一握の刃。最古の達人が常用した必殺の手口から、それは、つまり魔法使いたちが手を変え品を変えて繰り返す一撃は、そう呼ばれている。
帝国に侵略された村から命からがら逃げた一家。列車の切符が足らず、娘のミシェルだけが隣国に亡命できた。双子の兄との離別。亡命先で神父に拾われ教会で育つ。同じく教会にいる子供達の中で、唯一赤い髪と赤い瞳を持つミシェルはそれをバカにされ、なおかついじめられた。十五歳。学校へ。親から譲り受けた大事なペンダントを川に投げ捨てられ、仕返しとして石で番長格の後頭部を殴る。相手は死ぬ。ミシェルは刑務所行き。その国に少年院は無かった。後悔、罪の意識、そういったものは全く感じずにただただ世界を呪う。刑務所でもルームメイトにいじめられる。部屋のすみで呪詛を繰り返す。うるさいと蹴られ、ときおりキレる日々。レズの看守を誑しこんで脱走。脱獄は死刑。警察から隠れ続けなくてはならない。しかし誰かに見つかった。己の身がかわいい神父は助けてくれない。次はどこに逃げる。人のいない森に逃げ込んだが執拗に追われる。断崖まで逃げたところで追いついてきたのは警察ではなく、双子の兄だった。感涙しながら抱きつく。優しく撫でてくれる兄。戦争が終わったので故郷に帰ることになった。駅の検問を突破する秘策があるらしい。変装と偽造パスポートにより検問は抜けおおせたにも関わらず、駅のホームで、列車に乗ろうとしたところでかつての同級生と出会いミシェルの存在がバレる。始末しようと動こうとしたミシェルを兄が止める。大丈夫秘策がある。お前はこれをかぶって隠れていろ。あとで列車で落ち合おう。渡されたのはウィッグと着替え。トイレで着替えて篭る。やがて警察がトイレを調べに来たが、ミシェルに変装した兄が連れて行かれる。兄は警察に殴られすぎて死ぬ。変装したミシェルは涙をこらえながらその横を通り、列車へ。さようなら兄さん私は強く生きる。ばいばい。
- その何か
-
女の子だ。
肩にかかった髪がしゃらりと揺れた。唇がうごいた。何かを言おうとしている。聞こえないよ。どうしてそんなにうつむくの……。
モニター越しに僕を見ている。知っている。誰なんだろう。でも確かに会ったんだ。思い出せない。絶対に忘れちゃいけなかったことなんだ。既に失われて二度と手に入らないものを、ロストって言うんだって。苦しいよ。ねえ、苦しいよ。
「きあ……」
弦が切れるような、ひどく不快な音が駆け抜けた。だから女の子が何を言ったのか分からなかった。きっと分かりたくなかったんだ。さみしいよ。こっちに来ないで! 僕は震えている。怯えている。何に? 漆黒の魔女はロスティスって名乗った。孤独も怖くて他人も怖くて、僕は泣きたくなったんだ。そのとき飛びつくべき胸が無いことが、どんな息苦しさをもたらしたか。それを理解することだけが、僕に僕を繋ぎとめていた。
彼女は懸命に、何かを言って、手を伸ばして……無駄なのに……それでも諦めないでいる。天国を信じている。駄目だよ。僕のためなんだね。手を取り合って共有したものを、取り戻そうとしているんだね。うん、楽しかったし、嬉しかった……ふざけるな地獄に落ちろ。そんなことは絶対に許さない。ぽたりぽたりと涙が落ちてゆく。僕は泣いている……彼女のそれと酷似したしずく。けど決定的に違うのはその熱量。寒すぎる……ここはどこなの?
「ずっと……」
アーキタイプ。ぼそぼそとつぶやく彼女は、むしろまるで悲しみのようだったんだ。冗談なんかじゃない。どうしようもなくそれはある。何が悲しかったのか分からないほどの悲しさ。苦しんでいることを自覚できないほどの苦しさ。そんなものが、雑音の連続に映されただけなのかも知れない。本当に記憶だったのかも分からない。あったかいスープをもらったことがある。毛布の中で呼吸だけを感じてた。嫌だよう嫌だよう嫌だよう、何もかもが急速にとがっていく!
「探してた。やっと……」
ふんわりとした感触に触れて、はっとなった。それは、優しくて優しくて、どこまでも許してもらえて、ロストが裏返ったかと思うほどの気持ちで、甘くって。だから引きずり込まれたら、取り返しがつかない。一度全てを得てしまったら、全てを捨てない限り二度と戻れない。僕は息を切らして朦朧としながらも、体のどこかで熱のない炎が、青白い炎が燃え上がるのを感じていて、それだけが本当に頼りになるもので、だから涙がぼろぼろ出てきて、二度と戻れないのはどっちの方向なのか分かんなくって、炎が示す先にあるものを信じて二度と戻らないって決意して、誰にも意味が分からなくって絶対に譲れなくって、かけがえが無いからこそ≪その何か≫をかなぐり捨てようとしている自分が理解できなくって、けれども信じるしかなくって、吐き気がして。
「み」
日付はおろか秒に至るまでの時刻を、今でも覚えている。
その瞬間の後、水を打ったように、すべてが静まり返ったんだ。悟ったような気はしなかった。ただ、片方の手に心地よい重たさが得られていた。
右とひだり、どっちの手にだったのかは教えてあげないよ。
苦しみは消えない。
(書いた日:2006/09/29)
「無くて七癖、有って四十八癖」の四十八癖目をどうしても見つけられなかった私は聖廟老子を尋ねて十仙楼へと足を踏み入れた。折しも三歩目で出会った山菜摘みの娘にかどかわされて「馬鹿かお前は」全千四百八十二冊を読破し最後の一文で案の定の適切な罵倒をかまされて膝を突く。目に飛び込んできた床の木目をヒントに楕円方程式の一般解の画期的な求解法を閃いて語るべき相手を探したものの、昨年の魔術師狩りで数式を解する者は絶滅していた。出会い頭に私の思考に触れて発狂した悟りの佐藤君の手を引き引き、薬草を取りに東の洞窟へ向かった。
(書いた日:2006/09/24)
「ちょっと待て」
「何だ」
「いや何でもない。本当に何でもなかった」
「そうか」
「ちょっと待て」
「何だ」
「いや何でもない。本当に何でもなかった」
「そうか」
「ちょっと待て」
「何だ」
「いや何でもない。本当に何でもなかった」
「そうか」
「ちょっと待て」
「何だ」
「いや何でもない。本当に何でもなかった」
「そうか」
「お前の力は100ポイントだけだ。だから101ポイント以上のことは出来ない」
「分かった。いいよ。じゃあ100ポイントの力しか無いにも関わらず101ポイント以上のことをする方法を探そう」
「ダメだ。お前はルールを外れたことを為すことは出来ない」
「分かった。いいよ。じゃあルールの枠内で、100ポイントの力しか無いにも関わらず101ポイント以上のことをする方法を探そう」
「ダメだ。お前は何をしても101ポイント以上のことは出来ない」
「分かった。いいよ。じゃあ100ポイントのことしかしてないのに、101ポイント以上の価値になることをしよう」
「ダメだ。お前は何をしてもそれは101ポイント以上のことにはならない」
「分かった。いいよ。じゃあ101ポイント以上のことを出来る人を探そう」
「ダメだ。そういうのもお前の行動の範疇に含まれる」
「分かった。いいよ。じゃあ100.0999ポイントのことでもしてみようかな」
「訂正だ。お前は自分のポイントより大きいことを出来ない」
「分かった。いいよ。じゃあ僕のポイントを上げよう」
「ダメだ。お前は自分のポイントを上げることは出来ない」
「分かった。いいよ。じゃあもうポイント以外のことをするよ」
「ダメだ。お前のすることは全部ポイントで評価される」
「分かった。いいよ」
「どうだ。どうだ。あきらめるか?」
「いんや。あきらめる気は無いね。まだまだ出来ることはあるよ」
「言ってみろ。ぜんぶ否定してやる」
「その前にその減らず口を塞いであげるよ」
「ダメだ。お前は私の口を塞げなもごっ」
「……」
「んー、んー、んー!!」
「……」
「……ぷはあっ、はあ、はあ、はあ……何をするのだ!」
「なんだろね。ねえ」
「……何だ?」
「何ポイント?」
「……何がだ?」
「今の、何ポイント?」
「……」
「今の僕の行為は、何ポイントだった?」
「……んんんん、0点、0点だ!」
「ふーん……ずいぶん安いんだね、きみのくちびるは」
「0点だ! ダメだ!」
そして富士山が爆発した。おわり
- ひとつの石ころ
-
日も高い平日に、あなたは河原を歩いていました。
河原にはたくさんの石が、見渡す限りに転がっていました。あなたはふと、そのうちの一つに目を止めました。それは他の石に比べ、ほんの少しだけ暗い色をしていました。
あなたは何も思いませんでした。
あなたには知る由もありませんが、それはただの石ではありませんでした。そこに転がっているたくさんの石は、三万年前の火山の噴火で流れたマグマが冷え固まって岩となり、砕けていったものでした。しかしあなたが見たその石は、二十三億八千万年も前に同じように発現してから今に至るまで、奇跡的にその形をほとんど変えずに残り、ここに流れ着いたものでした。組成こそ似ていますが、周りにあるものよりも、硬度・粘度ともに非常に高いものでした。その石は、気の遠くなるほど長い地球の変化を、その肌に感じ続けていたのでした。二十三億八千万年間の光と音と衝撃を、その石は、構成分子の振動よりもずっとずっと小さな形で、覚えていました。しかしそのかすかな残滓はもう、記録としてはあまりにも変質しすぎていました。どのような技術、どのような知性をもってしても、そこから情報を復元することはできません。厳密に言えば意味消失はしていないのですが、復元のために必要な情報は、あなたがたが認識できるほどマクロな情報として観測することは不可能なほどに微小な世界にまで落ち込んでいました。そこは天使の扉の向こう側であり、人間などがいくら手を伸ばしても届くことは無い場所なのです。石はたくさんのことを知っていました。何種類もの生物が栄えては滅んだこと、そのなかに愛と憎悪に似たパターンが何度となく見られたこと、大自然は誰かにとっては時に醜いものであったこと、誰もそれを終わらせられなかったこと、砂を流せばどれかひと粒は頂点に来るような必然性で、しかし意味もなく人間種族が生まれたこと、彼らが流した血の赤さは彼らにしか認識できなかったこと、どのような時でもずっと風は吹き続けていたこと、いつか鳥が落ちたこと……ぜんぶ覚えていました。
しかし、石がそれを語ることはありません。今から何億年という時間が経った後にその石が、いつか砕けることがあっても、その断面は静かでしょう。粉々になり砂になっても、すべての記憶は何者とも共有されることは無いままであることでしょう。何の意味もありません。
しかし、何の意味も無いにも関わらず、その石は、存在しているのでした。それだけです。ただ、それだけです。それは、あなたに対していかなる積極的な刺激も与えることがありません。しかし、あります。結果的なバタフライ効果を除けば、この世の何者にも意味のある影響を与えることはないでしょう。にも関わらず、それは、そこにあるのでした。
それはずっと、そこにあり続けるのでした。ころりと。
めでたし めでたし
- 魔王に捧げる複雑な夢
-
彼女は夜を見ていた。
魔女になるためのアプローチは二通りある。
一つは知性を高めること。思考を無数に分化させ、それぞれが独立しながらも互いに関与する集合体とし、また、それらが活動すべき物理的な肉体とフィールドを含めて一つの世界とし、世界の中にはまた世界を想像する者が現われ、その階層化された世界の総数が三千を越えたあたりで、言うは安くも得るは難しい「魔力」の意味を理解できるのだという。
もう一つはその正逆。馬鹿の極限になること。ただし馬鹿といっても単純であってはいけない。情報とその結びつきとその構造によって鍛え上げられ洗練された「知」に対しての正逆でなければならないから、その愚かさは複雑だ。深遠の彼方に届くほどの馬鹿でなければならない。どれだけ考えても、分からない者には一生分からない。
そしてそれらを彼女自身が認めれば、その者は晴れて魔女となれる。ただ認めればいいというのではない。自分の中のどこかにある空洞、その中から確かに感じられる、より高次の存在。存在するとしないとに関わらず仰がれる意思。そいつの許可がいる。そいつは抽象の極限という意味で神に近いが、善でもなければ太陽でもない。ゆえにワールドは、便宜上それを魔王と呼んでいる。
そこは地獄か天国か。毒々しいまでに輝く星空の下。赤子の産声のような風が吹きすさぶ場所。傷つけるだけ傷つけて無責任にうち捨てられた罵詈雑言の山脈の頂で。ワールドは剣のように鋭く突き出た岩の先に、その腹を貫かれて七色の星を見ていた。呼吸を試みれば口から血があふれ出す。拷問そのものとも言える激痛の中で、彼女はそれでも笑わなければならなかった。それはこの世で最も尊き存在としての矜持だから。才能も富も愛も幸福も、そして≪言語かされ得ぬべき何か≫までも、生まれたときから全て与えられて誰よりも恵まれた存在、世界の名を関する彼女が、自らの意思で選択し受け入れたその境遇を、ひとときでも不幸だと嘆くようなことがあれば、この世の全ての生けとし生ける者たちの立場というものが無くなってしまう。一度はラストヘヴンの境地まで達した身。この先どれだけ苦しもうとも、どれだけのものを失おうとも、笑い続けていられる自信が彼女にはあった。
ここは概念界。物質ではない、という意味ではネットワークやデータベース、ハイウェイ、涅槃、黄泉、イデア界、数理空間に近い。だが情報が行きかう世界としても確たるルールが無い割には、脳髄を通して現実世界にフィードバックされ得るという点で他のモデル世界や世界モデルに比べて特異だった。そしてその由来もまた霧向こうの人影のように怪しい。ワールドが魔女になるための舞台として「開いた」この世界。果たして「開いた」という動詞の意味するところは何か。ワールドが思考の末に創案したからこの世界が「生まれた」のか、それとも、この世界が既に「在る」からワールドがそこに思い至ったのか。現に認めざるを得ないほどにそれは厳然と存在しているにもかかわらず、由来が分からない。まるで虚数のようだった。
概念界には誰もいない。いるのは彼女だけだ。彼女はすべてを作る存在になりたかった。しかしすべてを作るためには、彼女が作っていない全てのものが邪魔であった。だから原始に帰還した。何もかもが生み出される前のその領域へ。その行為は時間の遡行に似ているが、ここには時間もまた、ない。この説明で時間や因果が使われているとしたらそれは、あらゆるものを表現できない「言語」の制約にその責任は帰するものであり、また、そんなものを使ってしかものを表現できない人の身ゆえに仕方なきこと、とご容赦いただき、道具のせいにする不甲斐なさをもまた、どうか看過して頂きたい。
かつて彼女――ワールドには影があった。ワールドとその影は対照的な存在だ。ワールドに名はあるが影には無い。ワールドが至高の「知」の存在であるのに対し、影は低落の「愚」だ。だが、そのその対象性の中で一番特徴的なのは、存在の有無であろう。ワールドはいる。しかし、影は、いないのだ。そのことから影も形も無い、という慣用句が生まれたくらいだ。もしかしたら、ワールドが知りえないゆえに決して交わらぬ別の次元においては、それが反転していることはあるのかも知れない。影がいて、ワールドがいない世界。対照であるが同一ではない鏡の向こうのように。そこでは、馬鹿が馬鹿なりに世界を作るのであろう。ワールドも影も互いに交わらず、一人であり、孤独の条件に当てはまる者だったが、そこのとについて何も思っていなかった。それを知らなかったから。
ワールドは想像する。あらゆることを想像しなければならない。概念は分化し、概念は概念を生み出し、概念は別の概念と結びつくことでひとつ高次の概念となり、結びつきが構成を編むことでさらに複雑な構造の概念となる。想像すればするほど増えていく。ワールドは自らに無限の記憶容量と無限の可能性の処理機能を定義していたが、単式思考ではすぐに行き詰った。そこで、「広がり」と「運動」のある世界空間を新たに定義し、その中に増殖しながら変化する無数の精霊を放ってワールドのサブ思考とした。サブ思考がサブ思考同士で馴れ合う様を見て、彼女は初めてそれと対になる孤独という概念に思い至ったし、自分が孤独であることを知った。ともあれサブ思考は増え続け複雑化し続けたが、ワールドの意識はそれらのすべてを捉えて制御している。だがすぐに限界がきた。いや、サブ思考の増殖そのものは彼女の無限の思考力を脅かすことは無かったが、彼女がそうした複雑な思考をめぐらせているうちに思いついたより高度な概念のいくつかについては、その群式思考ですら、原理的に処理不可能であることが群式思考内で証明された。またひと工夫しなければならない。魔女は全てを生み出せる。その指先に不可能があってはならない。
サブ思考の複雑度を、さらに先へと推し進める必要があった。彼女自身ですらそれを把握しきれないほど多様に。またそのサブ思考体には、自身の思考に集中してもらわなければならないから、複雑極まるワールドの思考内容を知られてはならない。知れば必ずそいつらは、その底なしの情報量に混乱する。かくて生まれたサブ思考のハイエンドは、一時的にではあるが彼女から完全に切り離された。彼らには思考させるだけさせて、その思考が終焉を迎えた時点で、そのリザルトを持ってこさせて彼女自身にまた再統合すればよい。さよならまたね、と彼女はキスをした。単体で複雑という境地に達することが可能なほど高度な思考力を得たのと引き換えに、ワールドと切り離された種族に。「思考せよ」――その使命を与えられた種族に。
やがてその種族はものに名前を与えるようになり、また、自分たちの存在にも名前を与えることとなった。
彼女は夢を見続けている。魔王に捧げる複雑な夢を。そして笑っている。
- [0]
-
あなたはただの人間だ。呪力を持っていない。
- 1へ
- [1]
-
闇の中にいる。ブレーカーが落ちたらしい。落雷のせいだろう。数秒後、おぞましい異音と共にマシンが再起動した。テレビ(※ディスプレイの俗称)も電源が復帰する。ノイズの中になにかが写る。昼の公園だった。ホームビデオだろうか。画面右下に日付が表示されている。ただし、年/月/日ではない。映りが悪い。くもり空。少女が写っている。白のワンピース。高い鼻とブルーの瞳。表情からはわずかにだけ照れが見える。何らかの声が聞こえる。
テレビの中の少女と目があった気がした。凝視されている。少女がつぶやく。静かに。
「………〜。〜…〜〜〜?」
- マシンの電源を落とす 8へ
- 声に応えてみる 6へ
- 席を立ちこの場から去る 4へ
- [2]
-
「****」
あなたは名を名乗った。少女はなにごとかつぶやいた後、あなたの名を反復した。
「〜…〜〜、****。……****」
途端に、あなたは苦しみを感じた。呼吸が出来ない。肺の動かし方を失念。どうにもならない。意識は苦痛から希薄に取って代わられる。少女が笑った。優しく。やわらかに。天使のように。それを見ながらあなたは気を失う。あなたは絶命した。
- ENDy
- [3]
-
少女が目をふせた。悲しげに。まるであなたが彼女を傷つけているとでも言いたげに。どうしたものかと目を落とすと、あなたは電話を手にしていたことに気づいた。少女は気づいていない。しかしあなたは確信した。電話をしない方がいい。してはならない。取り返しのつかないことになる。
- 電話する 9へ
- 少女に笑いかける 5へ
- 席を立ちこの場から去る 4へ
- [4]
-
あなたはそこから立ち去った。外に出た。雨が降っていた。あなたは濡れる。やることは決まっている。あなたはさっそく道路に身を投げた。そして轢死した。
- ENDy
- [5]
-
少女は嬉しそうに微笑みを返した。あなたは確信した。いい子だ。少女がまた何かを言った。そして手を差し伸べてきた。小さく華奢な手が、画面いっぱいに広がる。あなたはそれに
- 触れる 7へ
- 席を立ちこの場から去る 4へ
- [6]
-
少女はふしぎそうに首を傾げた。あなたの声は届いているが、言葉の意味は理解されていないようだ。
- 名乗ってみる 2へ
- 笑いかける 5へ
- 沈黙する 3へ
- [7]
-
「〜〜、*〜〜、***」
テレビに触れて、あなたは本当に少女の手に触れた気がした。そして次に、少女に関するいくつかのことを妄想した。白のワンピース。病弱。助けを求めている。ぬくもりを求めている。あなたと分かり合いたいと思っている。そうすれば彼女は助かる。あなたは
- 名乗ってみる 2へ
- 席を立ちこの場から去る 4へ
- [8]
-
電源を落とせなかった。とても面倒くさい。ボタンを押すだけでいい。それができない。それほどまでに億劫。
- 少女の声に応えてみる 6へ
- 席を立ちこの場から去る 4へ
- [9]
-
あなたは電話した。そして用件だけ告げて切った。うつむいていた少女がはっと顔を上げた。だがもう遅い。少女の右こめかみから何かが散った。そのままどさりと倒れる。画面はそれを追う。少女は横倒しに倒れている。右手右足を下にして。こめかみに穴が見えた。顔のあたりから紅が広がっていく。
そしてあなたは正気を取り戻した。
- ENDies
- ATフィーリング
-
「――ATフィールド!?」
「そう。心の光。なんぴとにも侵されない聖なる領域。リリンも知っているんだろう? ATフィールドは誰もが持っている心の壁だということを」
「分からない……分からないよカヲル君!」
「どうしてだい?」
「え?」
「どうして分からないんだい? 分からないことがあるならそれを聞けばいい。言語というものがリリンが生んだ最大の罪悪だったとしても、それがあるからリリンたちは何とか互いを繋いでいられるのだから」
「だって……だってATフィールドはエヴァと使徒しか使えないはずじゃないか! なんでカヲル君が使えるのさ!」
「葛城さんの話を聞いてなかったのかい? 僕は使徒なんだ。ATフィールドは使えて当然さ。問題ない。この論理に死角なしさ」
「あ、そっか」
「そうだろう?」
「うん。そうだったね」
「だろう?」
「いや……いや、でも! カヲル君はさっき『誰もが持っている心の壁』って言ったじゃないか!」
「……それがどうかしたのかい、シンジ君」
「誰もが、ってことは当然、僕もその心の壁を持っているはずだよね。そうだよねカヲル君」
「そうだよ、碇シンジ君」
「でも僕はATフィールドを使えない。使えないよ。使えないんだ! ひどいよカヲル君!」
「違うよシンジ君」
「違わない! あたかもATフィールドが誰でも使えるかのような言い方をして期待させて、その後で人がどれだけ落胆すると思ってるんだ! エヴァに乗ってる僕だって超能力には憧れるさ! カヲル君みたいに浮いたりエヴァをリモートで動かしたりATフィールド越しにニヤニヤしたりしたいよ! けれど冷静に考えて、そんなこと無理に決まってるって悟ったときのスーパーガッカリ感を君は知っていてそんなことを言うのか? 優しい口調で近づいて、心を許したところで手のひらを返すカヲル君のその陰険なやり口が僕は許せない!」
「シンジ君、落ち着くんだ。きみは勘違いをしている」
「ふざけんなこれが落ち着いてなんかいられるか! うわああああああ」
「君だって生まれながらにして、ATフィールドの保護下にあるんだよ」
「この期に及んでなお、どうしてカヲル君はそんなウソをつくのさ!」
「ウソじゃないよシンジ君。本当さ。泡を想像してみてほしい。それぞれの泡の中の空洞がリリンたち一人一人と言っていい。そしてその周りを球状の膜が覆っている。これがATフィールドだ。ATフィールドがあるから、リリンたちは内と外とを分け隔てて、個を保っていられる。泡と泡が接しても、平面の膜が互いの空洞を遮断する。しかしこれが破られたとしたらどうだろうか。想像してごらん。どうなる? ……そう。その通りだ。分かるよね、」
「分からないよ! カヲル君が何を言っているか分からないよ! 分からないんだよ! カヲル君の言っていることはいつも分からない! どうして普通に説明できないのさ。誤魔化してるつもり!? それともわざと難しいことを言って僕を馬鹿にしているのか!?」
「シンジ君。僕は、きみの苦しみを理解することも無くすことも出来ないけれど、包んであげることなら出来るよ」
「どうしてそんなにズレてるんだよカヲル君は! 女の子にさんざん傷つけられて誰でもいいから優しくして欲しい今の僕の精神状態で言えばホモくさいのは背に腹は代えられぬってことで許容できるとしてもだ、いいか、君は僕を裏切ってるんだ! それをいけしゃあしゃあと包みこんであげるなんてどの口で言ってるんだよカヲル君! この口か! この口か! くそっ忌々しいATフィールドめ、僕以外ばかり守るのに僕のことは傷つけるときた! いいかいカヲル君、それにだ、僕は苦しみだとかそれを無くすだとかそういう話はしてないんだよ、カヲル君の言ってることが分からないって言ってるんだよ。ちゃ・ん・と、説明しろって言ってるんだよ! 分かるように! 納得できるように! そもそもリリンって何なんだよ!」
「君たちのことさ」
「はあ!? そんなぞんざいな説明でも分からないよ! 『君たち』って、どの範囲を指して言ってるんだよ! ○○チルドレン? ネルフ? 日本人? 人間? 動物? 生物?」
「君たちの……言葉で言えば『人間』ということになるね」
「じゃあ最初っからそう言えよ!」
「でもそれは正確な呼称とは言えないんだよ、シンジ君。君たちは自分のことを『人間』と呼んでいるけれど、そもそも『人間』というのは」
「知らねええええええええええよ! 通じる言葉を使えよ!」
「ガラスのように神経質だね、君の心は」
「なんだって!?」
「ウザいってことさ」
「こ……殺してやる!」
「やめた方がいい。君自身を傷つけることになるだけだ」
「うわあ、やっぱりATフィールドが僕を阻む!」
「そう。すべての悪意を拒絶する絶対の結界さ。誰も敗れない。ゆえに絶対領域。最強。マジ強い」
「僕は!? 結局僕はそれ、できないの!?」
「うっひょーやっぱりATフィールドは最高だよシンジ君! 超セーフティ! 安心すぎる! 死ぬ気がしないね! シンジ菌も伝染しない!」
「ひどいよカヲル君!」
- 爆発太郎
-
爆発太郎は爆発の業を背負って生まれた爆発人間だ。彼の望む最大のものが手に入ろうとするその寸前に爆発するがその定め。飛散した種子は風に乗って見知らぬ国の女に着床する。生まれた子もまた爆発者となり、血は誘爆の連鎖の中で継がれていく。
爆発因子を持つとして殺された母の骸から弾け出でた太郎は、母の仇を討つために上京した矢先にティッシュをくれた女に恋をする。慣れぬ空気に鼻を噛み噛み仇討ちのことも忘れ、生まれつきの破裂するような見目良さで女を軽く篭絡したものの、口づけの寸前に爆裂四散。爆発因子を大量に被曝した女は保健所に捕縛されたのちに見知らぬ島へ流された。爆発因子に脳まで犯された女が見る核終焉のビジョンは夢か使命か、導火線を辿る心持ちで高い高い山を上り詰め、火口にその身を投げる。
山は天を貫く勢いで噴火した。ああエクスプロージョンなるかなエクスプロージョンなるかな。爆発の道、ここに極まれり。
- セカンド意味
-
おじいさんは山へ芝刈りに行く前に自分の一生を省みた。何を成すこともなく生きてきて、ここまで老いさらばえた自分を。
一体なんだったのか。
人並みに幸せな一生を選択したことのどこに問題があるのか。問題などあるものか。無為というならばどうすれば良かったのか、そしてそもそも良いとはどういうことなのか。遅ればせながらも一生に一度の奇跡で≪ジ・アンサー≫がおじいさんの頭に訪れかけたが、おばあさんがはよ行けとせかすのでおじいさんの焦点は生活現実に戻された。得られかけた微かな灯火は吹き消され、桃太郎騒動のうやむやで雑忙に紛れ、意味消失した。
- 『ぶっ殺し太郎』
-
ぶっ殺し太郎はいつもまじめに丁稚をやっていましたが、ある日突然すべてが嫌になって、たまたま通りかかった人の頭を金鎚で叩き割ってぶっ殺してしまいました。
その時ぶっ殺し太郎は、とんでもないことをしてしまったと思いましたが、でもまあいいやと思いました。ところがそこに通りかかって現場を目撃した女の人がうるさくわめくので、そいつもぶっ殺してしまいました。太郎はふらっとそこを去りましたが、凶器の金鎚を手放す気にはなれなかったので、そのまま持って家に帰りました。
家で太郎を出迎えた女房が、太郎が手にしていた血まみれの金鎚を見て驚いて「あんた、ぶっ殺したわね! あれほど口をすっぱくしてぶっ殺すなって言ったのに!!」とわめくので、太郎は金鎚を力いっぱい振るい、自分の女房をもぶっ殺してしまいました。
一人娘もそこにいたので太郎はついでに娘もぶっ殺そうかと思いましたが、娘は脱兎のごとく逃げ出してしまいまいした。別に個人的な恨みがあるわけではないので、太郎はまあいいやと思いました。
太郎はその後も、老若男女構わずに人々をぶっ殺し続けます。岡っ引きをぶっ殺し、坊主をぶっ殺し、魚屋をぶっ殺し、女郎をぶっ殺し、太郎の歩いた後には屍だけしか残りませんでした。
そしてとうとう太郎は、その国のお城に単身乗り込んで、警護の兵もものともせず、殿様の頭をその手に馴染んだ金鎚で粉々にし、ぶっ殺しました。
行く所まで行き着いた……そう感慨に浸ろうとしたその瞬間、太郎は後頭部に衝撃を受けて倒れました。気を失う前に見たその狼藉者の姿は、なんと殺し損ねた彼の娘、ぶっ殺し花子でした。彼女もまだ幼いとは言え、ぶっ殺し一族の血を継いでいる、言わばぶっ殺し娘だったのです。
太郎は、ぶっ殺し一族の名に恥じない娘の姿に満足し、誰もお前を止められない、とつぶやいて息を引き取りました。それを冷たく見下ろしていた娘は、あっそ、と言い捨てながら父が持っていた金鎚を拾い上げ、そこを去りました。
めでたし めでたし
- ヒストリーアウト
-
そこはヒストリーアウトと呼ばれている墓場だった。あったことをなかったことにする力によって葬られたあったことたちがうち捨てられている。そこでクリューサは恋人に手紙を書いていた。
ヒストリーアウトは静かな海のような、あるいは寒々しい虚空が広がる宇宙のような、波一つたたない場所だった。なかったことになったことだけがあるところであるため、そのなかったことの存在を認識することで存在させる自我や心などと呼ばれるようなものは存在しえなかった。
しかし彼女の胸は金属製の棒で貫かれて血を流している。それは矛であり、矛盾を成立させる二点武装のうちの一点であり、因果の管理者が世界の整合性を保つために、このヒストリーアウトに蹴りだしたイレギュラーだ。そして、恋人に忘れられた上に存在を抹消されてしまったクリューサに突き刺さり、心が無いことに対して矛盾する形で、クリューサにふたたび心が宿った。
クリューサの恋人は、もはやクリューサを覚えていないどころか、元から彼女を知らない。そんな彼にクリューサは愛をしたためている。だがその手紙が、どこに届くというのだろう。ヒストリーアウトにいるものが、元の世界に遡行するのは不可能である。いや、その可能性はゼロではないが……それには、元の世界で、なかったことになったことと全く同じことが起きるという途方も無い偶然を望まなければならない。規模は違えど、海原に瓶を投げるようなものだった。
あるときある場所で、前世を持たない娘が生まれた。
気がつけば私は、そこに蔓延する灰すべてを吸い込んでいた。
正誤を象った像を踏みつけて広場の中心から、八方に転がる死体を見渡す。誰も助からなかった。この薄暗い世界を悪夢と形容した老人も、窒息して死体の数をインクリメントさせた。私には分からない。悪夢という言葉もこの曇り空も、現象としてしか認識できなかった。現象であるから、恋人の睦言とも氷山の凋落とも変わらずに意味が無い。
「シャンタール!」
名を呼ばれて振り向いた。劇場に続くカフォシア・ストリートの彼方から、粒子を飛散させる銀の光がこちらに突進してきた。一瞬だけ私の視界がダウンして、巨大な二文字が圧迫感を持って目の前でゆらめく。希望。意識はすぐに錆色の街に引き戻される。銀の光は羽根の生えた馬を駆った男に握られていた。
「覚悟!」
希望は明確な敵意を持って私を攻撃してきた。私は絶望の側に置かれている。別にいい。灰色の世界は私自身の心情を表しているとは思わなかった。
私はつい、と人さし指を立てて愚撃を受け止めた。時間の一瞬の硬直の後、軽く力を入れて銀を砕く。指一本でなければならなかった。悲しみも喜びも超えて圧倒的優位であることが私の条件だったから、楽勝や余裕を少しでも妥協したら罅割れてしまう。私は一歩だけ移動して銀の主の背後に回った。たくましい腕を握ってそのまま引き千切る。飛び散る血に降られる前に、もう一歩だけ踏み込んで全く関係が無い屋根に離脱する。何でもない。失われた感慨をこの男から奪うと決めた。噴水の横に着地した男は、私を見上げて睨み付けている。意思だ、なるほどこの男は私に殺されたとしても力強い。対して私は、どんなにこの男をねじ伏せたとしても無力であろう。無力なまま私は世界を握りつぶす。私は私が存在すると思っている拠り所がまぼろしであることを知っている。戯れに息を吐いてみたら、それもすぐに拡散した。
人の心には天使と悪魔の両方が巣食っているという。私はいずれも持っていない。地の果てまですべてが燃えた記憶だけがある。
武器を失った希望は勇猛過ぎた。彼は最大の近接攻撃を私に浴びせることで、私に直に触れてしまった。すぐに失速し、ぐずぐずと灰になって落ちた。
もう希望は無い。私は悲しみを伴わずに涙を流した。屍を踏み越える。その愉悦を理解してくれる何者かを求めて。
- おじいさんと畑
-
天気のいい朝だった。
その日も、おじいさんはいつものように畑で仕事を始めようとした。半年後の良き実りを想像しながら、ざく、と鍬を振り下ろした。
おじいさんはもう一度土に鍬を入れようとした。そのとき異変に気がついた。鍬が土を食ったまま抜けないのだ。力を入れて抜こうとしたが、だめだった。次に、思いっきり力を入れたが、抜けなかった。しかもそれだけではなかった。鍬が手から離れない。そして気がついた。そもそも、おじいさんの体そのものが全く動かなくなっている。
鍬に寄りかかるような体勢のまま……おじいさんは畑で立ち尽くしていた。おじいさんは何度も動こうと試みたが、すべて失敗に終わった。そして日が暮れた。
次の日もおじいさんは、畑で硬直していた。鳥が勝手に畑に入ってきて、おじいさんが撒いた種をついばんだ。それを見ておじいさんは、この畑は実らせることは出来なくなるのだろうか、と思った。
何日経っても、何ヶ月経っても、何年経っても、おじいさんは動けなかった。おじいさんは豊かな大地と、遠くの山々と、広い空を見ていた。また、朝に太陽が昇るのと、夜に太陽が沈みんで月や星が現れるのを見ていた。もはや動くことはあきらめていた。
やがて畑の周りに家が建った。人が集まり、町ができた。道路が引かれ、車が走るようになった。鉄道も引かれて、さらに人が増えた。ビルが建ち、夜にはネオンの輝きが溢れ、眠らない街になった。また、人々や、乗り物や、建物の景観が周期的に変化を繰り返すのを見ていた。時間はどんどん加速していき、おじいさんは文化の盛衰や、歴史が目まぐるしく移り変わっていくのを見続けながら、自分は死んでしまったのだろうか……と考えた。死んだから、動けずにいるのだろうか。死とは、何も出来ずに世界を見せられ続けることなのだろうか。死後の世界とは、見る者を無視してただ変わり続けるものなのだろうか。しかし、いくら考えても、答えが出ることは無かった。
人々は不思議と、畑には手を出さなかった。おじいさんも、畑も、誰にも気づかれていないかのように干渉されなかった。ただ、一度だけ、畑の前を通りかかった少女と目が合ったことがあった。少女はふ、と笑ったかと思うと、ペコリとお辞儀をして去っていった。おじいさんは分からなかった。
争いがあったらしい。街は攻撃を受け、建物という建物が崩壊した。人々は死んだか、どこかに行ってしまった。さらに月日が流れ、地震や津波が起こり、畑の周りはふたたび平原になった。畑以外は荒野だ。草木一本生えない死の大地だ。大地にはヒビが入った。やがてそのヒビが覆い尽くした。そのうち大地の一部が、ドスン、と抜け落ちた。欠けたパズルのピースのように。そこから自壊は連鎖していった。大地はガラガラと崩れた。そのまますべての大地は離散した。大気も霧散した。重力の絆はもはや断たれ、地球は完全に崩壊してしまった。四角い一区画を残して。
畑はずっとそのままだった。おじいさんも動けずにそのまま立っていた。終わりは来なかった。
鍬に寄りかかったおじいさんと、それを乗せた畑が、宇宙空間を漂っている。ゆっくりと自転しながら、太陽を中心とした巨大な楕円軌道の上を漂っている。
おじいさんは一人で畑に立ち、星々を見ている。
ずっと見続けている。
文:ポーン - 協力:ノラさん(2-N)
- 存在の淵
-
そこは、サボテンひとつ生えない砂漠だった。あるいは、人里離れた山奥だった。あるいは、誰も使わなくなった廃ビルの屋上だった。どこでも良かった。
男が仰向けに倒れていた。瀕死だった。息を絶やしそうになりながら、ぼんやりと月の空を見ている。
彼は使命を果たした。敵対者の執拗な追撃に耐えながらも、彼が所属する一派に極めて不利な生存競争の鍵となる少女を、敵対者の攻撃の届かない安全圏まで逃がすことに成功した。腹部に致命的な傷を受けながらも。
彼は彼の一派に貢献し、死のうとしている。それは、彼の一派の価値観からすればこの上なく立派で、美しい死に方だ。仲間たちの誰もが彼を称えるだろう。彼もまたそれを望んだ。そしてその通りの結末になった。彼は心の底から満足していた。彼は咳き込んだ。吐いた血を口外に出せずいよいよ溺れかけた。それは彼に強い肉体的苦痛をもたらした。だが、彼は呪わなかった。彼の一派の一機能となることを、儀式によって受け入れている。それは彼の心臓が動き続ける限り継続する。
だが、死の間際、すなわち彼が彼の一派から解放される瞬間に、彼はぼそりと一言つぶやいたのだった。それは禁忌だった。なぜなら、彼がその言葉を心に留めず口にした以上、それは彼以外の誰かに向けて発せられたものであり、また、ここに彼の言葉を聞きうる人間がいない以上、いかなる人間に対しても向けられていないものだったからだ。ならばその言葉は一体誰に向けて発せられたものなのか。もはや罪は明白だ。
「騙したな」
それで彼は事切れた。
彼のつぶやきに呼応するかのように、雨が降りだした。砂に染み、あるいは土に混ざり、あるいは石畳にへばり付いていた彼の血が、雨に溶けて希薄になっていく。
その頃、少女は泣いている。
- 幸福姫
-
女の子が木の椅子に座っている。
何かあるだろうか――いや、特に何も無い。西日が差す部屋で、女の子はただ考え事をしているだけだった。ゆっくりと、さして重要でもないことを考え続けていた。そして出た結論は、ひどく意味に乏しいものだった。
(そろそろお夕飯の支度をしないと)
が、そのとき全く別のどこかで、誰かがつぶやいた。
「……なんだそれは。」
地下の薄暗い部屋で、男がうつむいてぼそぼそと語るその呪詛は女の子には決して聞こえない。
「お夕飯? 馬鹿じゃないの? なにがお夕飯だよ。クソが。終わってるよこいつ。くだらないこと考えてんじゃねえよ。クソが。自殺しちまえ。手首を切れ。首を吊れ。線路に飛び込め。つり橋から落ちろ。早く死ねよ。俺は、お前が死んでほしくて死んでほしくて仕方が無いんだよ。ずっと待ってんの。ここで、指くわえて、ずっと見てんの。お前がもっと苦しめばいいのにって思う。本当に。クソが。お夕飯。はあ? お夕飯。あーお前の家が早く燃えろ。そのときにお前が逃げ出さなきゃいいのにって思う。だって逃げなければ、煙にまかれて、息が苦しくなって、炎にも炙られて、なんで逃げなかったんだろうって後悔しながらお前が苦しみながら死ぬから。その時お前は思うんだよ、お夕飯のことを考えていた自分が馬鹿だったって。そうだよお前は馬鹿なんだよ。気づくのが遅いんだよ。お前がもっと早くに自分が馬鹿だってことを悟っていたら、お前は自分が馬鹿であることを悩んで、苦しんで、殺されても殴られても侮辱されても仕方が無い人間なんだって、人として誰もが持っている何かをあきらめられたんだろうに。クソが。地獄に落ちろ。すべてを救う神様がたとえいたとしてもお前だけは助けてもらえないんだよ。いや違う、お前だけを助けないために、神様はほかのすべてを救うんだよ。お前だけ価値が無いんだ。ざまあ見ろ。死ねよ。」
女の子が木の椅子に座っている。
窓の外で何かが揺れている。
天井を見た。何か知らぬものが見えたわけではないが、彼女は小さく笑った。
女の子は愉悦していた。傍からはそうは見えないが、深い深い至福の中で、神、もしくはそう呼ばれるべきものに与えられた美しき状態を抱きしめていた。あまりに愉快であったため大笑いしそうになるのを、ずっとずっと抑制していた。十年以上前から。生まれたときから。
一人だった。
特にいいことがあった訳でもない。
女の子の、秘めたる無限の幸福に根拠は無い。幸福であるがゆえに幸福であるだけだった。仕方が無いのだ、最初から満ち足りているのだから。そして、これ以上何かを望もうとも思わない。どうせこの状態は続くから。まるで悪夢のように、終わる見通しも無いまま続くのだ。いつまでもいつまでも。
女の子は、自分の右手を見た。それは、何の変哲も無い右手だった。取り立てて目立つ特徴があるわけでもない。だが、おかしかった。ただあるだけでしかないと言うのに、ひどくおかしかった。
そして動かす。軽く握ったり、開いたりする。その結果、彼女は自分の右手が動くのを目撃することになる。それはただの動きでしかなかったが、しかしむしろだからこそ、とてつもない秘密が隠されているように見えた。女の子にとってそれは、世界の沈黙と同じく、すさまじく戦慄すべき事実か、素晴らしき奇跡であるように思えた。そこに自らの吐息が重なって、虚無の物語はいよいよ加熱されてゆく。彼女はこの小さな部屋で、主観の自由の極致に座していた。
やがて女の子は立ち上がった。腰掛けられていた椅子が少しずれて、その拍子に音を立てた。
女の子は知っているのだ。
自分が存在していることを。
自分が生きていることを。
自分が何かものを思っていることを。
――恐ろしいことに。
- 茄子
-

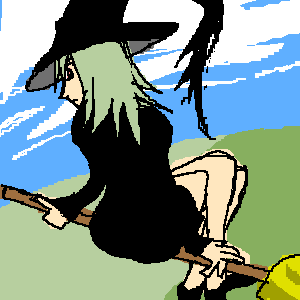
魔女さんがカボチャを探して飛んでいると
カボチャ畑につきました
魔女さんは適当なカボチャをたくさん取って
おうちにもってかえってパーティをしました
とてももりあがりました
でも翌日警察が来て
そいつらもみんなかぼちゃにしてしまいました
そしたらその日もパーティです
その次の日も次の日も
そのうち世界はかぼちゃだらけになって もうかぼちゃはこりごりだと魔女は思って
今度は茄子にしました
おしまい
絵:ポーン - 文:ノラさん(2-N)
自分で自分の行動の動機を明確にしようとしている限り、動機の大元は必ず心に辿り着く。他は無い。そしてすべての心を制御することは出来ない。ある心を制御できたとしても、そこには制御しようと思った動機があり、その大元はやはり心である。根源において、自分で自分が思うことや感じることは自分の自由には決してならない。
心の軍門に下るしかない。どれだけメタ昇ったところで心の鎖はその足に必ずついて回る。たとえ鎖を断ち切ったところで断ち切ったその手にやはり鎖がある。自分は心のためにしか生きられない。心は自分ではない。自分は自分のためには生きられない。
悩んでも無駄である。その無駄につけこんで思考はますますもって停止すべきものになる。考えない人間は死ねないし生きれない。生かされるか殺されるかしかできない。
自分とは何か。語るのも考えるのも心である。自分ではない。自分は心がものを感じ、語り、行動する様を無力に見続けることしか出来ない。それを現実にフィードバックすることはできない。ぼくは隔離されている。
この文章はぼくが書いたものではない。ぼくの心が書いたものだ。ぼくは何も思わない。ぼくの心がぼくを定義し、想像し、ぼくが何か思っていると仮定して、ぼくの思いを捏造して文章化したものだ。面白いのか? つまらないのか? ぼくは感想を持たない。どうでもいいとも思わない。感想は読まされただけで生じるものではない。
ぼくは何も思わない。ぼくはここにはいない。
神様がいるとは思わない。神様がいないとも思わない。
神様のことを思わない。
- 初動
-
「かの詩人はその精神に、常人には持ち得ない規模の憎悪を抱えています。またそれを吟じることにより、異界から魔物の群れを呼び寄せ続けています。詩人の下に集った剣士たちが降臨した魔物の群れを統制し、各地の神殿の破壊を目論んでいます。
神殿は現状の世界を維持するために不可欠の施設です。生きている神殿が減少すれば世界は変質し、3つ未満になれば世界は終了します。生きている神殿は全て合わせて六件のみです。神殿を新規建立する余力はありません。そのため神殿騎士たちは現存する神殿を全力で防衛していますが、無尽蔵に増加する魔物たちの兵力に圧倒されつつあり、突破されるのは時間の問題だという意見が有力です。
この終焉を回避する手段として、王立ネットワークはいくつかの案を挙げました。そのうちの一つが、今も魔物の群れを召喚し続けている詩人を暗殺する事です。
詩人の暗殺を実現するには、詩人の黒の詩情と対峙できる精神力と、生身で魔物たちを滅ぼせる戦闘能力とを兼ね備えた個人が必要です。実際問題としてむしろ前者の条件の方が満たし難いことから、その者が担当する役割は勇者と呼ばれています。
あなたがここに召喚されたのは、勇者となり得る可能性があるからです。
勇者による詩人の暗殺は、数ある解決案の中でも成功率が最低と見込まれているものです。しかも失敗すればおそらく担当者は死にます。しかし可能な案をすべて実行することで、世界が継続する可能性を高めることができます。
あなたの生命と時間を世界の継続確率に捧げてください。あなたはこの依頼を断ることはできません。なぜならあなたに授けた祝福は、あなたの生命を補足しているからです。もしあなたが設定された期限までに詩人を殺害できなければ、祝福はあなたを殺す効果を発揮します。この効果は絶対です。
あなたの忠誠心や思想は問われていません。詩人の暗殺に成功すれば、あなたに授けられた祝福は解除されます。詩人を暗殺するために、あなたに可能な最大の範囲で努力してください。よろしくお願いします。」
長髪の男が美しきエルフの髪を撫でている。エルフは居心地良さそうに目を閉じて、その寵愛を甘受している。
「もはや貴様らに対する私怨も無い……恨みがあるとすれば、姑息な計を弄したあの裏切り者に向けるのが筋というものだろう」
男は立ち上がり、こちらを振り向いて言った。
「我が城を占拠した裏切り者は、腕輪を始動させることで戦闘力を飛躍的に向上させている。残念ながら魔族には寝首をかかれるような隙は無い。奴を滅ぼすためには、それを十分に超える戦闘力を準備する必要がある。私は一度は腕輪を打ち破った貴様らの力を高く買っているし、この状態であれば貴様らと同質の戦い方をとることも出来る。小僧、必要とあらば貴様の指示に従ってもいい。私は貴様らに共闘を申し出る」
宿敵の突然の申し出に、仲間達はざわついた。人間と魔族が共闘? あり得ないことだ。互いに知っている。人間も、魔族も、等しく裏切りを好む種族であるということを。信じる心を抱いて自滅した愚かな宿屋の息子の例を引き合いに出すまでもない。
「ざけんなよ」
案の定、一向のリーダーと思しき緑の髪の少年が、半眼で吐き捨てた。
「既に忘れてんのか? 魔族の脳髄の構造は鶏と一緒か? ブランカの北の小さな村……そこでてめえは何をした? 無様に怒り狂って、そこの女を殺された腹いせにオレの故郷を気持ちよく蹂躙して、草木一本残さずに全壊させたのは誰だ?」
少年はいつの間に抜刀していたのか、歪な形状の聖剣をブンブンと振り回しながら長髪の男に歩み寄る。
「で何だ、てめえ部下の不始末を片付けんのに付き合えだ? は、どのツラ下げて言ってんだ。冗談もほどほどにしろよこのツリ目野郎。思い出させてやろうかエエオイ。誰が殺されたか。誰を殺したのか。何ならオレがこの手で、今すぐその女をブッ殺してやろうか!?」
「吼えるな小僧。貴様には何も出来ない」
「なんだと!?」
激情に歪んだ顔を、触れ合うほどに近づける。長髪の男は涼しい顔でそれを見返している。
「愛する者を守れなかった。共通点がある貴様とならば理解し合えると思ったのだがな」
「シンシアを殺したのはてめえだ!」
発作的に少年は長髪の男の体を、聖剣で容赦なく斬りつけた。男は避けようともしなかった。人間のそれと同色の液体が滴り落ちて芝生を汚す。
「違うぞ、それは……」
口の端から血を流しながら、男は目を細めて笑う。
「いいか。貴様が殺したんだ」
ゆっくりと、念を押すように重く発音する。致死文言。男は呪文を唱えている。
「何言ってやがる」
「貴様が殺したんだよ、ロト」
ザラキと呼んだ者もいる。毒針と呼んだ者もいる。自己欺瞞の一点を突いて精神をズタズタに掻き回す。破壊を生業とする魔族の秘儀。
「私と貴様の違いを教えてやろうか。貴様は、自らの命惜しさに愛する者を差し出したんだ!」
「黙れ」
「私にとって、人間の村一つには何の意味も無かった。私の標的は勇者だけだった。貴様一人を殺すだけでよかった」
「黙れっつってんだよ!」
「守れなかったと思っていたんだろう。違うな。貴様が死んでいれば、貴様の家族たちは死なずに済んだんだよ。無論、シンシアもだ」
「ああクソ、あああ……」
「なのに貴様は逃げた。隠れた。己の無力さを言い訳にして。貴様が死ねば良かったんだ」
「あああ――ニフラム!」
そして少年もまた、呪文を唱えた。己の心を守るために。
「? なんだそれは」
「ニフラムニフラムニフラム……」
繰り返す。死の文言が消え去るまで。忌まわしき過去が消え去るまで。目を閉じて繰り返す。何も見たくない。何も見なくていい。愛しきシンシアの言葉、心地よい記憶だけが少年の脳裏でリフレインする。
「ニフラムニフラムニフラムニフラム……」
「逃避か。見苦しいぞ勇者! 余興もここまでだ……アバカム!」
一心不乱につぶやく少年の胸に手のひらを当て、長髪の男は開錠の呪文を唱えた。少年が閉じこもっている暗い精神の地下室をこじ開けるために。だがその呪文は、男が予想だにしなかった作用を起こした。
「オハヨーゴザイマス。いー天気」
少年が、あーとうめきながら頭を振っていた。
「……なんでこう、魔族ってのは人間の、タチの悪いデフォルメみたいなアプローチばっかしてくるんかね」
一体どういう脈絡なのか。少年はこれまでの心境の変化を全く無視し、長髪の男を正視して不敵に笑っている。
「何だ……?」
「あ、いいもんめーっけ」
呑気な口調で少年はその場にしゃがみ込み、嬉しそうに聖剣を拾い上げる。さきほどの悶着で取り落とした、神竜によって力を引き出された魔王殺しの聖剣。
「何も出来ない? 失礼な。有限実行で証明しまっす。ザオリクありーの、世界樹ありーの、今さら重みある決断でもないさね」
少年はそのまま、男の後ろで状況を見守っていたエルフにつかつかと歩み寄った。そしておもむろに剣を掲げ、振り下ろす。エルフは倒れた。一撃で絶命した。絶句する男を尻目に少年は、ふさ、っと布状のものをエルフに被せる。布は、太陽の光を反射してきらきらと美しい模様を紡いでいる。
「光のドレス。知ってるよね? 永続マホカンタ。さて、今この女に呪文は一切無効です。よって呪文による蘇生は不可能。ザオリクでもザオラルでもメガザルでも! いいですねナチュラルですね、命の価値がどんどん高騰してます。そこで質問です、あなたは愛する人のために死ねますか? はいそこの魔王君」
「誰だ貴様は」
「さて誰でしょう。あと気づいてなさそうだから親切心で教えたげるけどね、さっきの質問はまた別の意味でマホカンタだから。カキン! 反射対象は糞ザラキ。さあたいへんだよ、答え間違うと即死亡! あーもう秒読みです。ハイ3、2、1」
「ま、待て、」
男が倒れる。流れる血の量が尋常でなくなる。
「ズドン! 積年のムカツキ、クリアしたりー!」
一匹の豚がいた
豚は豚には見えなかったが、そいつは自分が豚だと言い張った
心の芯を折られたことがある者特有の徹底性で
美しい鳴き声の裏に張り付いていた、醜い自己への裏返った愛
傷つけられ過ぎた豚は、近づく者すべてを傷つけた
傷つくこと構わず、豚に触れようとした者が一人
そいつは血の海に踏み込んで豚を拾い上げることに成功した
豚は呪いが解けて姫君に変じるということもなく、尚もぶうぶうとぐずったが、そいつに抱きしめられて静かになった
豚が美しい悲鳴を上げることはもうなくなったが、今は安らかな寝息を立てている
- デルタ袴田
-

「水際の乙女」
「白痴と盲目」
「魔王の影を踏むしもべ」
現象を引き起こすための言葉が連ねられる。
たった独りの人間が発する言葉であったが、魔韻は夜に残響し、復唱するようにして後の言葉と重なる。
「水際の乙女」
「闇に伏し」
「白痴と盲目」
「杖を捨て」
「魔王の影を踏むしもべ」
「狩人の心を奪え」
言葉は風に流されて溶けるが、その影響は確かに大気に混ざり、袴田が欲する現象を、世界に仕込んでいた。袴田は、壁の無い廃屋でひとりぼそぼそと唱えている。だから神も聞き逃す。しかしそれを耳ざとく捉える精霊がひとりあった。黒の海を切り裂くように泳ぐ、まっしろな蛇にも似たそれは、頭部が4つ又に別れていた。なにかに触れようと伸びる指のように。その腕は、魔王があまた持つもののうちの一振り。名をデルタと言った。
デルタは風が運んできた、逐次生成型の呪文のひと連なりを意味解釈する。細部を読む前に、全体に込められた意図を汲み取る。そこからは、呪文の唱え主が、無力であることと、その無力さを認識の中で無きものにしたいということが知れた。白をその属性とするデルタはこのような暗黒指向を好まない。呪文の唱え主を嫌悪した。
袴田の前に、とぐろを巻く白い腕が現出した。召喚に成功したのだ。感嘆の息は漏らさない。袴田は己の心を殺すつもりであったから。袴田は蛇に命じた。俺はお前に魂を捧げる。お前は俺に情報を捧げよ。我が意識の触手となり、我を世界の傍らに立たしめよ、と。
近年、魂の価値は高騰している。その取引についてデルタに損は無い。しかしデルタは気にくわなかった。蟲の良い話だ。この男は新しき眼を得る代償に不要なものを押し付けようとしている。むしろ、重たくなった心の破棄こそが目的であろう。が、良い。別に良い。矯正できるものならしているが、おそらくはもう手遅れだ。男の瞳は、いかなる誠意にも応えない、末期的な色に濁っていた。
男に白光が宿った。
袴田は右手を軽く動かす。そして、その動きを眺める。素晴らしいことだ、何もかも見える上に、何も我が心を苛まない。からからと笑った。脳髄が命じるままに。肉体が愉悦を感じている。
だが、その愉悦を読み取る魂は、もう無い。
- 先生と弟子
-
「くっ……まだまだ」
「満身創痍だな」
「そうですね。先生がやりました」
「立てるか?」
「はい!」
「まだ練習を続けられるか?」
「は……い!」
「我ながら残酷だ。貴様もこんな拷問によく耐えられるな」
「練習でありましょう。ぼくの筋を叩きなおしておられるのでしょう?」
「いや。憂さ晴らしだ」
「せ、先生!?」
「冗談だ。すべて意味があるから安心しろ。しかし驚いた」
「ぼくの才能にですか」
「いや。粘り強さだ。貴様の虚弱さを考えれば驚異的だ」
「めずらしい、先生がそんなお言葉を。正直照れます」
「勘違いするな。不思議に思っているだけだ。若さ、というだけでは片付けられない……貴様はこの五年、一度も弱音を吐かなかったな?」
「はい」
「なぜ折れない。なぜ続けられる。恨み人でもいるのか?」
「先生です」
「私をか。殺せるつもりか」
「いえ、そういうことではありません。先生がかわいいからです」
「私がか。血迷ったか」
「いいえ。酔狂でここまで耐え忍ぶことはできません。先生はすばらしくかわいいです」
「笑わせる。こんどは貴様がべんちゃらか」
「またも珍しいものを見た。照れておられるのですね」
「冗談にも程度があるぞ」
「本心ですが……まあ、いいでしょう。そういうことにしておいても。しかしぼくが男であることを考慮すれば、さすがにぼくの次の言葉は否定できますまい」
「言ってみろ」
「ぼくは、先生とまぐわりたいと思っておるのです」
「なんだと」
「性交渉です」
「なんだと」
「西の者ならば、確かセックスと言ったはず」
「セックス!」
「はい」
「男女の双方に愉悦をもたらす勝負であるという、あのセックスのことか!」
「さようです」
「セックス……セックス……」
「先生、雷に打たれたような顔をしないでください」
「貴様、私が誰だか分かって言っているのか」
「当代武流祖の師範代です」
「愚か者が! 貴様ごときが、この私とセックスをするなどと!」
「大したことではありますまい。少々触らせていただくだけです」
「本当に触るだけか!」
「正確に言うならば、揉ませても頂きます」
「本当に揉むだけか!」
「さらに正確に言うならば、挿入させても頂きます」
「ならん! 断じてならんぞ!」
「僭越ながら」
「ふん。次は何を言うつもりだ?」
「ぼくは先生を越えるつもりです」
「どこまでふざけたことを。保証してやる。貴様には無理だ」
「ぼくは先生を力でねじふせ、その素晴らしいお体にふるいつくつもりなのです」
「世間的には、強制姦通は犯罪であると聞くが」
「果たしてそうでしょうか」
「違うのか」
「ならば先生は、認められるのですか? ぼくが、先生に敵うという……その可能性を」
「貴様には無理だと言っている」
「本当に?」
「ああ」
「本当の、本当に?」
「くどい」
「ならば、もしぼくが力で先生を押し倒しても、文句は言いませんね?」
「出来るものならな。だが無理だ」
「これで明確になった……その言葉、忘れないでくださいね。ぼくは今後これを励みに、より一層きびしい訓練にも耐えることができましょう」
「なるほど、得心いった。つまるところ貴様のその、過剰な根性は……」
「はい」
「若さだったと言うわけか」
「先生」
「何だ」
「かわいいです」
「もういい」
「先生、かわいいです! 先生! 先生!」
「寄るな! 今までで一番無駄の無い動きをするのもやめろ!」
- 最強伝説創貴
-
やや、一部の分類の娯楽小説に傾倒していると指摘されれば反論 も出来ない言い方で表現するところの、今回の一連の事件の『犯人』 ――生活指導、後田反雄(うしろだそりお)――はその説教と称す る、説教とはとても呼べない稚拙な言い逃れを僕にことごとく論破 され、ついに反論の言葉を全滅させてキレて、その手に持ったバッ トを振り回して逆上してきた。 「口で言って分からない馬鹿は……体で分からせるしかないなああ ああああ!」 状況は実にくだらない。時は放課後。場所は体育倉庫。周りに人 気は皆無。この狂った暴力教師に対して、僕はたった一人で対峙し ている。下僕は一人も連れてきていない。持ち駒は無く、裸のキン グ一枚がここに佇む――ついでに言えば武器となるような道具も魔 法も持参してきてはいない。 、、、、、、、、、 だが武器ならばある。 「供儀、供儀、供儀ぃぃぃぃ! まさか貴様、ここから生きて帰し てもらえると思っているのか? 思っているよな? 思っているだ ろうとも!! だが、だが甘ぁぁぁい、俺はハンパじゃない、半端 な指導は始動しないとも!! この≪一発号≫を貴様の脳天に振り 下ろし、腕でも足でも肩でも肋骨でも鳩尾でも心臓でもなく紛れも 無い脳天に叩きつけ、粉微塵にし、木っ端微塵にし、跡形も残さず、 塵も残さず、貴様という存在を無に強制的に共生させ、矯正を共成 してくれる!」 笑わせてくれる。どこまで素敵な教育方針だ。そんなものがまか り通るのなら、僕だって国を作るのに苦労はしない。やれやれ、 『口で言って分からない馬鹿は、体で分からせるしかない』か…… 、、、、、 全く同感だ。 「死、ッイ、イ、ぬ、ぅ、えぇ、い!!」 雄たけびと共に、後田のバットが、僕の脳天めがけて、振り下ろ され――た。 砕け散った。 「ひゃっはああああ、いいぃぃぃいい音ぉぉぉ!!」 砕け散った――ただし後田のバットが。後田が≪一発号≫と名づ けていたその生徒撲殺用金属物体が、粉微塵になり、木っ端微塵に なり、木の葉が風に舞うように、サハラ砂漠の砂塵がテントを打つ ように、パラパラと、周囲の空間を落ちていった。 「砕け散った、砕け散った、砕け散らせてやったぁぁあはあははは ははは……は?」 とても意外なことに、とてもとても予想外なことに、その時の後 田の顔は、そこそこの見物だった。自慢の、そして生徒を震え上が らせてきた後田の唯一のアイデンティティの≪一発号≫を僕のデコ ピン一発で否定された時の後田の顔は、これ以上なく滑稽で、不覚 にも笑ってしまいそうになるほど醜い様相を見せ、凍てついていた。 もう2回ほど、ピン、ピン、と空で指を弾いた。風が舞う。 僕は、指先ひとつで、後田の時を止めたのだ。うん、テスト結果 としては悪くない。全く期待通り、見込みどおりの威力と効果だ。 誤解のないように言っておくが、これは魔法ではない。 こういう時のために体を鍛えてきた。こういう時のために、りす かと別れたあの日から武術の鍛錬を一日たりとも緩むことなく継続 し、研ぎ澄ませてきた。武器とは僕自身の拳のことだ。小学生のこ ろ、頭でっかち、とは誰かに言われたが余計なお世話だ。そんなこ とは僕自身が最も理解していた。となれば、それを克服する努力を 僕がしないはずがあるまい。いや、克服というのも大袈裟か。僕は ただ、僕の肉体的な脆弱さに対応しただけだ。瓦の十枚や二十枚、 素手で割れなくてなにが人間か。 「き、き、貴様ぁー!!」 きっかり一分後の沈黙のあと、後田が再び動き出し、僕に殴りか かってきた。この時、僕は動かず、それを冷たく見据えながら、三 重に後田を軽蔑する。 ひとつ、その弱さ。伝家の宝刀が砕け散ったとは言え、悲しいほ どに力強さを欠いたその拳。 ふたつ、その醜さ。これはもうさんざん述べている。改めて繰り 返し説明するにも値しない、唾棄すべき現実だ。 そしてみっつ、その愚かさ。せっかく≪一発号≫がその身を呈し て、僕という存在の強大さと、己という存在の矮小さを教えてくれ たというのに、その現実を認めようとせず、むしろその事実から逃 げるように、己が弱さを無意識の底に追いやってチンケなプライド を死守すべく、僕に歯向かってきたこと。少しでも未来を思うなら、 後田は即座に土下座して額を床に擦り付け、むせび泣きながら僕に 謝罪をするべきだった。そのくらいの誠意を見せられれば、僕にだ って慈悲はある、両腕両足を力ずくでもぎ取り、両目を抉って両耳 の穴にコンクリートを流し込み、舌を引き千切って鼻の穴に詰める 程度で許してやったさ。 だが後田は間違えた。間違えにも気づかず間違えて、僕の怒りを 買ってしまった。もはや哀れむしかない。後田の拳があと数センチ で僕の鼻の頭に届くというところで、僕はやれやれと動き出す。ふ ん。なんてザマだ。軽蔑する理由をもうひとつ見つけてしまった。 惰人間のものにしても、あまりにお粗末なその速度。この拳、蝿は そんなところには止まりはしないが、僕が蝿なら止まるね。僕は僕 自身の体が完全に始動する前に、後田にそっと別れを告げた。 「さよならだ」 そして――僕の拳が煉獄を紡ぐ。
(文章:ポーン / 原案:孫悟空大王さん)
- ロレンとマドカ
-
「あなたはだめですか。どうしても……」
すべての人間が音声会話をメインコミュニケーションとしていた時代より幾星霜。人の人たる本質――呪縛と名づけられた未解析パターン――は、変わらずに世を支配していた。蒼き演繹のフェルネルシアの一角で基底レベルチャンネルを開いていた二人も、その例外ではなかった。h:炉錬に受け入れられようと、PP円が己のすべてを吐露して訴える。
「私はお慕い申し上げております。炉錬様を。古より、恒久的に。にもかかわらず、あなたは否と言う。あなたは拒絶する。私を。条件、次で述べるもの、を満たしたときに。私が近づく。あなたに。あるレベルのライン以上に」
h:炉錬は冷たく答える。
「俺はおもう。以下のように。あなたは冒されている。低俗な感傷に。むろん、俺は知らない。原因、それに至ったもの、を。もしくは、必然性、あなたがそれを欲したもの、を。俺は存在している。シークエンス、『外挿』と呼ばれるもの、のエグゼキューターとして。円さん、申し訳ない。俺はこたえられない。あなたの思慕に。同じく恒久的に」
そう言う炉錬の胸中には、確かにわだかまり、未練、苦々しさがあった。だから炉錬は円に対し、その表現を遮断する。神のシークエンスのエグゼキューターが精神的惰弱さを他人に吐露するなど、あってはならないことだからだ。
「h:炉錬様。h:炉錬様。h:炉錬様……」
炉錬は密かにため息をついた。円が哀れすぎた。円が己の望みを叶えるために選んでいるのは、最も低級な戦略だ。すなわち、相手の絶対名を反復してコールすることで、相手の精神の門戸をノックする。確かに、神のシークエンスのエグゼキューターに高級攻撃が通用するはずもない以上、それが最もポジティブな方法であるとは言える。言葉だけなら幾らでも届く。だが悲しい。円が最もすべきなのは、なるべく早くあきらめることだ。可能であれば今すぐに。そうした場合が、最も傷が少ない。しかし炉錬は理解している。円にはそれができないのだ。想いの強さに支配され、その想いに反する選択肢を自己の中で提案することすら出来なくなっている。
炉錬は、円が自らに振り降ろせない斧を、代わりに振るってやることにした。いつものように。
「あなたは勝手に繰り返していれば良い。その行為を。次の理由は無い。俺があなたと話し続ける。これ以上。ゆえに、俺は切断する。このチャンネルを。しかし、最後に、俺は謝罪する。申し訳ない」
と、その時――PP円の声色※ が変わった。
「……本当に?」
それは炉錬が初めて見る異変だった。異変に興味を持って炉錬は、チャンネルの切断を遅らせた。
それが命運を分けた。
「あなたは嘘つきです。割り切っているフリなんかして」
「俺は次のことが分からない。何か、あなたが言っているもの」
「分からないのは当然です。炉錬様は悲しみから逃げておられます。今朝、なついていた■が死にました。静かに横たわっていた。あんなに可愛かったのに、その■はもう動かないのです。どう思います? 反応できないでしょう」
(俺は感じる。言葉を。言われた。円によって。とても古いものであると。原始言語……?)
円の言葉の韻律は、炉錬の聞きなれないものになった。いったいどこの、いつの言葉だったのか。炉錬は得体の知れない奇妙さを感じ、普段は滅多に触らない領域から、辞書を引っ張りだした。なまじ中途半端に意味が分かる言葉は、無意識を撹乱するからだ。
「炉錬様は分かってない、しかし、本当は分かっているはずです。私を拒絶すれば炉錬様は、もう二度と私には会えない」
炉錬は、円の言葉を9割理解する。くだらないことを言っている。しかし先ほどの■というのは、何を指す言葉なのか見当もつかなかった。今は失われた語彙のようだ。想像しようにも、それに類似する概念は、今や影も形もありはしない。
「俺には無い。感傷。言われるような。あなたによって」
「違うわ。そんなことを言うのは、さみしさを知っている証拠よ」
この、円の論理は破綻している。炉錬は態度を変えない。実を言うと円の言うとおりで、炉錬は確かに、円の報われない思慕とそれをただ看過するしかない自己に対し、根深い虚しさを覚えてはいる。炉錬はそのことを自覚している。だがそれは円には分からないはずだ。一切の心理情報は遮断しているから、見破られるはずが無い。円の確信めいた口調は、要はハッタリだ。あるいは本当に確信があるのかも知れないが、だとしたらそれはオカルトだ。どちらにせよ、証拠が無いのだから尻尾が捕まれることはあるまい……h:炉錬はそう思った。
「炉錬様、そんなことはないでしょうに」
「!?」
今の円の言葉にばかりは、炉錬も驚愕せざるを得なかった。その声が、己の内から聴こえてきたからだ。聞く必要は無い。聞く必要がある。こればっかりは、直視せざるを得ない。耳を傾けざるを得ない。
「何者か。お前は!?」
円――PP円は、雪原の吐息のように、深く深く答えた。心の底から答えた。
「私は何者か。あなたにとっての意味を申し上げるならば、私は、あなたをお慕い申し上げる者です。膝をつき、頭を垂れ、あなたにかしづく者です。残念ながらそれは純粋な崇敬では無い……渇望、情欲、自意識、それらは消しても消えない。だから私は禁を破った」
「次の気か。あなたは同化する。俺に」
「それが、私の、一番の望みですから」
「それは無理だ。俺は拒絶する。お前を」
「それは誰の気持ちだったかしら?」
「あなたのものではない」
「あなたのものでもない」
『たった一人だったのか、合わせて一人だったのか……』
***
「!」
「あら、おはよう」
その言葉を聞いて、炉錬は、安堵した。それは、古から伝わる慣用句だった。正常系で起動した者に対して言うものだ。つまり言われた炉錬は、重大な破損は抱えていないということだ。
「俺は見た。悪い夢を」
「私は知っているわ。それを。だから私は消したわ。それを」
「俺は感謝する。謂者を」
「わたしは思う。水臭く。次はお互い様よ。私たちが困ったとき」
キーン、と冷えた雰囲気がする。炉錬は、もはや恐怖とはならない寂しさを、心の中で弄んだ。誰かの存在が消し去られた時に特有の、敬虔な気分にさせる空気。誰かが炉錬をおびやかしていた。だがその者は、もういない。いなくなった。いなかったことになった。
「どんな者だった? その者の名は?」
「私は教えない」
「何故だ」
「私は嫌よ。次に拘ることを。無かったこと」
「俺は、知れなくなった。もう二度と……」
炉錬の、追悼するようなつぶやきは、既に安全を確保したからこそ、発せられるものであった。
※比喩
殺されたロクサーヌはとても幸福だった。彼女は思い通りに生き、思い通りに振る舞っていた。そして思い通りに死んだ。死に方、死に様まで、自らの思い通りに導いて。一方、激情にかられて彼女を殺したシークはひどい絶望の中に沈んだ。それまで彼が大切にしてきた全て――地位、財産、家族、婚約者、それと窓際に置いていた小さな鉢――を捨ててロクサーヌを選んだ時、彼の胸は希望に満ち満ちていた。たった一つの欲しいものを手に入れるための行為であれば、たとえそれが他の全てを失う事であっても、その者を心の底から満足させるのだ。しかし、身軽になったなどとうそぶきながら意気揚々と彼女を迎えにいった彼を待ち受けていたのは、あってはならない最悪の裏切りだった。ドアを開けて彼は見た。シークの親友ビヘイビアの口づけを受け、恍惚に身を震わせていたロクサーヌ。シークは「何で……」と言った。
ロクサーヌは言わば、生まれながらの魔女だった。彼女はシークを愛していた。窓越しに見つけた彼を見初め、デーデルタの階段で劇的な出会いを演出し、恐るべき忍耐力で時間をかけて彼の気を引き、嘘で塗り固めた秘密を打ち明けて彼に究極の二択を迫った。それまでの全てか、ロクサーヌか。過去か、未来か。彼は未来を選んだ。その時ロクサーヌが感じたのは安堵ではなく納得であった。彼女はシークが全てを捨てることを知っていた。信じていたのではなく、見抜いていたのだ。ロクサーヌの欲望は激しかった。彼女は愛情を際限なく求めた。円満な愛よりも無私の愛を。無私の愛よりも破滅の愛を。そして破滅の愛よりもむしろ深い憎悪を。ビヘイビアはそのために誘惑し利用しただけだった。ビヘイビアはロクサーヌにとってはつまらない男で、彼に抱かれる事にロクサーヌは嫌悪を覚えたが、それがシークを傷つける最良の手段だと理解していたロクサーヌは、嫌な顔ひとつ見せずに嫌悪に耐えた。
「ロクサーヌは自分の気を引こうとしているだけだ」――甘い口づけを交わす二人を目の当たりにして、そんな都合のいい想像を思いつくことはシークにはもちろん出来なかった。
ロクサーヌに仕込まれた通りにビヘイビアは怒鳴る。「俺たちは結ばれた。お前は選ばれなかった。ここは俺たちの部屋だ。神に祝福された部屋だ。お前が汚していい場所ではない。ここはお前のいるべき場所ではない。今すぐに立ち去れ!」ビヘイビアは剣を持ってシークを追い返そうとした。追い詰められたシークは反射的に剣を抜き、ビヘイビアを殺してしまった。そのままロクサーヌを見つめて立ち尽くす。
ロクサーヌは愉悦の中で泣き叫ぶ。ビヘイビアの死体にすがりつく。シークを愛しているがゆえに、ビヘイビアの名を何度も呼ぶ。どうして殺したのと泣き叫ぶ。どうして、どうして、と繰り返す。それは本心でないことを除けば魂の叫びに等しかった。それはシークの心を壊す呪文だった。「どうして」――どうしてこんなことになったのか、分からないのはシークの方だった。彼女はシークの中に芽生えた根源的な疑問を何度も何度もコールする。シークの中に「どうして」が渦巻く。シークの中に「どうして」が溢れ返る。どうして自分はここにいるのか、どうして彼女はここにいるのか、どうして自分は絶望しているのか、どうして自分は生きているのか、どうして世界は存在しているのか――何もかもがシークには分からなかった。一方ロクサーヌは、シークの絶望を完全に理解していた。シークは足元が崩れて独りになったが、ロクサーヌはそんなシークに同調して至福を享受した。
ロクサーヌはシークに自分を殺させた。
シークとロクサーヌ、二人は相思相愛だった。シークはそれを知らなかった。ロクサーヌだけがそれを知っていた。その愛し方は正反対と言えるくらいに違っていた。
美しく作成された空と大地を後にして、最初の洞窟に足を踏み入れた時に主人公は、≪松明≫を。
道具として持っておらず、ふくろにすら入っていなかったのに、どこからともなく取り出した。
一体何の義理があってか、掲げられた≪松明≫は当然のように、闇を照らした。
なんと洞窟は奥まで続いていた。「ここには“何か”がある」と言わんばかりの景観で。
- 呪われし姫君
-
少年は一息ついた。目の前にある古びた扉の向こうが最奥だ。嘆きの搭を上り詰めた彼は最上階の一角で、決戦に備えて自分の状態を確認した。
体の至るところが軋み、傷だらけなのは別に問題ではない。若干の時間をとって呪文を使用すれば、その満身創痍は解決できる。その際に消耗される精神力も微々たるものだ。むしろ本当に問題なのは、自分がたった一人であることだった。『ひとり』――それは致命的だ。今から足を踏み入れるような重要な拠点では、それぞれに守護者が配備されていることが多い。守護者たちは例外なく異常な体力と戦闘能力を揮って襲いかかってくる。これらを撃破するためには、頼もしい仲間たちとの連携は欠かせなかった。
仲間はいた。嘆きの搭に挑む前は彼ら三人と一緒に戦い、頻出する魔物を余裕で駆逐していった。搭を見上げて一緒に茶化したことも覚えている。だが今は違う。彼らは三人とも死んでしまっている。原因は戦闘中の過失だ。残念ながら少年は死人を蘇生させる手段を持ち合わせておらず、この状態を回復することは出来ない。悔やんでも意味が無いが、ひどく悔やましい。
一人で戦い続けてきた。
「仕方ないか」
こぼれる弱音すらも一人では虚しい。元気づける者もうるさがる者もそこにはいない。本当に仕方なく、少年は気持ちを切り替えた。ここで心を折ってしまうのは、今まで支えてくれてきた仲間達の気持ちを踏みにじるのと等しい。
『戦わなければならない』――それは確かに義務感だ。その義務感を定義したのが、自分自身だったのか、それとも周りの人間から与えられたものだったのか、それは自分でももう分からない。どちらも否定しがたく、真実であるような気もする。いずれにせよ確かなのは、少年が、その義務感を抑圧だと感じたことが無いということだった。前向きに生きるしかないという事実は、彼の心にむしろ勇気をもたらしていた。
苦しみも痛みも、彼の味方だ。最も重要な奥のレベルにおいては、この世には味方しか存在しない。それは……それだけは、間違わない。
彼は扉を開けた。鍵を使うまでもなく、それは簡単に開いた。
「ここは……」
闇だった。暗くて何も見えない。少年は松明を掲げた。闇の奥を知ろうと、目を凝らす。
何も見えない。だから少年はその空間の中に踏み入り、もっと目を凝らした。
まだ何も見えない。だから少年はもっと奥に踏み入って、さらに目を凝らした。
後ろで、扉がバタンと閉まる音がした。だから少年はもっともっと奥に踏み入り、さらにもっと目を凝らした。
何かが見えた。
「いみ」
声が聞こえた。くぐもっていて、男か女か分からない声だ。暗がりの向こうに見えている、何かの方から聞こえてきた。少年は近づいた。
「誰かいるのか?」
その何かは、なんだかよく分からない。まだ暗く、まだ遠い。しかし先ほどの声がそちらから聞こえていたのはほぼ確実だった。と、思う。『意味』……と言っていたのか? 意味が分からない。まだ。だから確かめる。
もっと近づく。まだ遠い。だけどおぼろげだった輪郭が、なんとなく定まってくる。人? そういう感じ。人ではないかも知れないが、近寄れば分かることだ。だから歩を進める。
「あく」
また聞こえた。か細く、弱々しく、消えてしまいそうな小さい声。『悪』と言っていたように聞こえなくもない。もしかしたら言葉ではないのかも知れないが。
「しず」
「くわ」
「まう」
声は断続する。それはなんだか、悲しい調べに似ていた。とりあえず少年は、いちいち意味を考えたりはせず、言葉を返したりもせず、黙ってそれに近づいた。それが何なのかを確かめるために。踏み込んだ足元で、ぴちゃっと音がした。何か濡れたものを踏んだようだ。視線を落とすと、床が濡れていたのが分かった。液体が、そこらじゅうに広がっている。知りたくないことを知ったときのような匂いがしてくる。
それは大量の血だった。血の池が、向こうの『何者か』を中心に広がっている。構わず少年はその何者かに近づく。ぴちゃっぴちゃっと、跳ね散らかす足音が続く。少年は近づいて近づいて、それが何なのか、ようやく見えるところまで来た。そして歩みを止めた。足音も止まった。
おぞましいものを見た。
「てる」
何者かは、壁際にいた。何者かは、目を閉じて横たわっていた。何者かは、はだしだった。何者かは、何らかのことをつぶやいていた。何者かは、血に濡れたドレスを纏っていた。何者かは、亜麻色の髪も血にぬらしていた。何者かは、血色の良い体を横たえて、まるで眠っているかのようでもあった。何者かは、この場所に溶け込んでいた。何者かは、高潮した頬をたたえていた。何者かは、リューシャの紋章がしつらえられたブローチを胸元につけていた。何者かは、失踪した王女であった。何者かは、死んではいなかった。何者かは、絶望していた。
カタカタと音がした。それは奥から聞こえてきたものだった。奥……どこの奥? 分からない。この空間のさらに奥か。それとも、自分の心の奥からか……同じことだ。少年は気づいた。自分は震えている。だらしなく、恐怖に神経を揺さぶられている。
何だこれは。
何が起こっている。一体どういう残酷な事実が、ここに横たわっている。何ということだ。どうしてこういう事が起こる。どういう複雑な過程の事情がこんな酷い状態を築いたというのか。いい加減にしろ。おかしい。どうかしている。あんまりだ。あまりにも酷い。
マレーネ姫がいる。
この状況は、どれだけの希望を打ち砕こうというのだろうか。運命宿命神人間生命大自然大宇宙海空大地、そして呪詛、そして自分、あまりにみずみずしく素晴らしいものを、つらい思いをしながらも楽しく享受してきた自分には気づくことは出来なかった。こうして目の当たりにするまで。分かりやすく見せつけられるまで。自分は馬鹿だ。なんて馬鹿なんだ。欺かれていたのか。こんな惨状が存在するなんて、聞いていない。誰も教えてくれなかった。当たり前だ。こんなものは誰にも伝えられない。伝達不能、いかなる説明からも剥離する、万象の裏をかいた虚偽の真実、アッタコトナノカ、ソレトモナカッタコトナノカ……
「こんなに寒くて禍々しくて、光の射さないどんづまりに一人で……いや≪独りで≫閉じこもって――」
この世には、こんなものすら存在するのか。こんなに弱く、どうしようもなく頼りなく、救済を待ち続けるしかないような、いや、それすらも望まず、ただ、
それはそれは少年の心をずたずたに塗りつぶす、
「この世の中には敵しかいないと、思っておられたのか」
ここにはあの恒例の、邪悪なる守護者はいなかった。マレーネ姫は誘拐された訳ではない。自らここに閉じこもっていたのだ。愛されていたにもかかわらず、それを知っていたのか知らなかったのか、彼女が欲したのは、完全なる孤独。世界にあまねく存在している自分以外のすべてから逃げおおせて、嘆きに身を震わせ、悪夢に身を浸して。無明の自虐の中にある愉悦に欲情して。
寒々しい光景をつくって釘付けにする、搭の呪い。その本質は目に見えることはない。精神のみに対して作用するからだ。少年に呪いは通じなかった。仲間がいた、信頼があった、意志の光で退けることができる、取るに足らない罠だった。一人になった今でも、見えているのは血の幻覚までだ。だがあるのだ、呪いを自ら呼び込み、招き、受け入れ、囚えられ、繋がれた鎖に接吻する、夜深く超越してしまう精神が。
こんなものに、出会ってはいけなかったのかも知れない。だが皮肉なことに、少年は希望を捨てられなかった。恐怖しながら、もし自分がこのような嘆きの中で嘆くような人種だったらとほんの少し想像するだけでも暗黒極まる可能性にめまいを覚えながら、少年は、マレーネ姫の体にやっとの思いで手を伸ばした。抱きかかえる、ドレスからイメージの血が滴る、床の血だまりに呑まれる……
「くる」
救える訳がない、救わないで欲しい、と、マレーネ姫は言葉なく言った。彼女は真性の孤独であり、あらゆるものから断絶されているので、こちらの存在に気づいているはずもないし、こちらに語りかけることも決してできない。だがとにかく、独りにしてくれ、と確かに姫は言った。少年はたったそれだけで切り刻まれて自分を失いかけた。恐ろしいほどのこの弱さ。だが、すんでのところでその嘆願を拒絶する。すみません。それだけは聞き入れられません。少年はまだ、生きている。
姫が光満ちる正気の世界にひきずり戻されるか、それとも、少年が暗黒の誘いに篭絡されて深く堕ちるか。この先に待つのはそのいずれかしか有り得ない。一方は冷たすぎるし、もう一方は熱すぎた。そして驚くべきことに、二人とも、人間なのであった。
少年は蝕まれている。
空も海も大地もなく、ただ呪われし姫君。
肩に落ちた水滴が刺すように冷たくても、声を出さない。声を出すことに意味はない。体を貫いている数十本の矢も、刺さったまま放っておいてある。流れ去った血を追って手を伸ばすこともしない。
井戸の底で、神を待つかのように、じっと座っている。
動けない。助けは来ない。もうすぐ死ぬ。出来ることは何も無い。
しかしこれらは、絶望や残酷を意味するものではなかった。腐りかけている彼の体の中、感じるものもほとんど失った彼の心の中には、まだ炎が残っていた。
大切な人を守った。意志の残滓が、ちろちろとか細く、しかししぶとく、線香花火のように爆ぜ続けている。
彼はまだ笑えた。
「正直、俺には分からんなあ。なんせ間が独特でしょ」
「えー? 面白くないですか?」
「これ、君に薦めたのって、誰」
「お母さん。」
「ふうん。君、お母さんと仲いい?」
「え?」
「お母さんとケンカしたことある?」
「……なにが言いたいんですか」
ある所に、つまらない少年が一人いた。少年はかなりの馬鹿で、しかもプライドが高かった。それゆえに少年は、自分がつまらない人間であることを理解できなかった。うすうす気づいてはいたくせに、馬鹿特有の自己欺瞞を発動させ、自分を直視することから逃げ続けていた。何年も何年も。
唐突な展開で恐縮だが、そんなクズの結晶のような少年に、一体なぜなのか、どういう奇跡があったのか、恋人ができた。しかも不思議なことにその相手は、大変に魅力的な少女だった。また、それに加えて賢かった。高嶺の花が落ちてきた。分不相応とはまさにこのことを言う。この不自然極まりない事実を前に少年は、あろうことか、ただ浮かれた。喜び狂って食いついた。何も考えなかった。何も疑問に思わなかった。
蜜月の日々と言って良かった。優れた少女は劣った少年を愛した。劣った少年は優れた少女に夢中になった。その優劣について、少女は触れなかったし、少年は気づいていなかった。それで二人は上手くいっていた。数ヶ月の日々のうちに、二人の距離は、おおむね順当なステップで近づいていった。
ある日少年は、少女に数冊のノートを見せた。ノートは、これまで少年が書き溜めていた小説だった。少女はそれを読んでみた。その内容は、一言で表すと『僕は特別です』というものだった。よほど勘の悪い者でなければ、そこに過剰な自意識が放つ腐敗臭を嗅ぎつけることができただろう。凡庸そのものだ。少女がその悪臭に気づかない道理は無かったはずだ。しかし彼女は、顔をしかめたりはしなかった。それどころか、レベルが低い上に書きかけばかりの中途半端な文章を、少女は丹念に読んだ。忍耐強く読んだ。欄外の無意味なつぶやきまで、一字一句残さず。すべて読み終えてから、少女は言った。「きみの考えていることは、すごく面白いとおもう。もっと読みたい」。少年はさらに浮かれた。
少女は、少年の頭の悪さにこそ目をつけ、愛した。少年は頭が悪いので、現実を、自分にとって都合が良いようにしか解釈できなかった。それは主に、自分の世界観から他人の価値観や意志を排除することによって成り立つ解釈だった。要は独りよがりだ。その歪んだ解釈が生み出す、現実と認識とのズレ。少女は少年が書いた文章を優しく褒めながら、それとなく方法論を混ぜ、そのズレを拡大する方法を少年に教えた。ズレは少年の手により意図的に拡大されることで、正誤という評価軸とは無縁の価値を持つようになった。少年の小説はクズだったが、少女の手により、ある程度好意的で波長が合う読者であればなんとか『読める』ものになっていったのだ。しかしそれでも、少年が馬鹿であることには変わりはなかった。少年はそれが、すべて自分の手柄であると思い込んでいた。
少年は本当に馬鹿だった。初めて一作を書き上げただけで少年は、自分には才能があると思った。その事を信じて少年は、小説をもっともっと書くようになった。それまでは少女と会っていた時間も、小説を書くことにあてるようになった。そのくせテレビゲームはやめなかった。
繰り返すが、少年は本当に馬鹿だった。少年は、自分が特別だと思った。自分は小説を書くために生きている人間だと思った。そのために、少女が邪魔だと思った。自分の時間を占有するからだ。少年は自分のことしか考えていなかった。しかもこの糞馬鹿野郎は、そのことを実際に口にした。少女に向かって。
「悪いけど、できれば、僕の足を引っ張らないで欲しい」。
少女は顔を真っ赤にして、目に涙をため、しかし「ごめん」と言った。少女は類まれな忍耐強さと寛容さを持ち合わせていたのだ。それに対し少年は、呆れたことに、怒った。ただ相手を傷つけて責めたいだけの、ただ怒りたいがためだけの怒り。一体なにをどうすれば、これほどまでに醜い人間ができあがるのか。怒った勢いで少年が、具体的にどんなことを少女にしたのか、わざわざここに書くことはしない。
この話に一つ謎があるとすれば、こんな少年をなぜ少女は愛せたのか、だろう。しかしそれは、脳が膿んでいる少年の知れるところではなかった。少女は何度か少年に電話をかけたが、少年はその度に、拒絶した。しかも、言わなくてもいいことを言って、わざわざ相手を傷つけて。訂正する。少年は馬鹿ではない。最悪だった。なおかつ大馬鹿だった。
少女は人並み外れて寛容だったが、さすがに人間だった。仏の顔も三度まで。彼女は我慢の限界に達し、これまでで初めて少年を責め立てた。筋道立てて丁寧に、静かな口調で、少年の醜さや愚かさを並べ立てた。それでも恐るべきは、少女が少年を責めながらもまだ、解決を考えていたことだろう。少年の非を指摘しながらも『ではどうすればいいのか』というところまで語っていた。少女はとても前向きで、知的で、誠実だった。
だがしかし残念ながら、救いようのないことに、少年は、少女のその誠実さを上回るほどの大馬鹿だった。少年は図星を突かれ、プライドを傷つけられたことに耐えられなかった。自分が言い返せないのが分かると、悪態をついてその場を立ち去った。少年は、少女から逃げ出したのだ。そのとき少女は、どのくらい情けない気持ちになったのだろう。もちろん少年はそんなことを想像できない。なぜなら馬鹿だから。
個人的に、彼は死んだ方がいいと思う。だが彼は死んでいない。今ものうのうと生きている。そしてつまらないものを作っては、一人で悦に入っている。
しかしながら彼の自己欺瞞も限界に近づいていた。自分がどれだけ過剰に恵まれていたのかにやっと気がついて、自分がこれまで犯してきた糞な振る舞いを、いまさらになって後悔し始めるという糞っぷり。幸福への道を自分で壊しておきながら、それで招いた不幸を嘆く。何やってんだ。アホか。まさに救えない。
死ねよ。
- ソーダ
-
静かな日だった。向こうの青い空に、煙が立ち昇っているのが見えた。
あれは、紗江の家の方だ。私は小走りになった。手に提げているケーキの箱も、あまり丁寧には運べなかった。
「紗江」
アパートは燃えていた。窓という窓から煙が出ている。時折それは竜の口のように、勢い良く火を噴く。きっと中は炎で満ちているのだろう。燃えるものはみな燃えているのだろう。その中には、人も含まれているのだろう。
「何やってんだ! おい、誰かこいつを止めるんだ!」
見知らぬ老人に怒鳴られた。人間を捨てれば地獄を獲得した意味がなくなる。私は振り払い、見えない壁に突き進んでいた。実際は別の男に止められているだけだった。
疲れた。
私は座る。気になることはない。老人が私の顔を覗き込んだ。
「気をしっかり持つんだよ」
何かと、何かを天秤にかけている。愛。これは愛だ。寄せて返す波が時間差で遠くの砂浜まで届いているかのような巨大な気持ちにずっとこれまで包まれていたのを、私はこのとき初めて自覚した。闇には暗い闇と、より暗い闇がある。気になることはない。それは真実であり、また虚偽でもある。私は一人ではない。
左腕の蚯蚓腫れが疼いた。彼女は平凡から一つだけ外れた方法で他人を愛す。私は意味ばかり見ようとしていて、形として見えているものを看過しすぎた。結局宿命を欲する私の心は、単純な答えに落ち着いた。
彼女は、私を傷つけすぎた。そして罰を受けたのだ。私は燃えるアパートを見上げた。太陽の光で逆行になってよく見えない。それは絶対性の誇示。一連の状況に神の手が介在している証拠だった。
私は彼女の死など望んでいない。しかしそれを保証できるのは無意識の影がかからない部分までの話だ。傷つけたい、殺したい、絶望させたい。心外だとしか思えないそれらの怨念に、私は知らずと支配されている可能性がある。神は笑っている。
あって当然だったものが消えうせ、それまで抑えられていたものが空いた玉座にすべりこむ。
「無駄な試みだと思うよ」
悲しみを含んだ声が、聞こえた気がした。悪意などではない、優しい哀れみが感じられる声だった。私は空を見ようとして、顔を上方に向けた。電線にカラスが一匹、止まっていた。カラスは私を見ていた。
「自分から始めた覚えは無かったとしても、降りられるもんじゃない」
私はただ、大声をあげた。カラスは羽ばたき、逃げるようにして飛んでいった。
箱を開けてみる。ケーキは、思ったよりも型崩れを起こしていなかった。行儀も忘れてかぶりつきながら、私は思い出していた。
いつか砂浜を歩いていた。
- シンシアーズ・ファントム
-
ドラクエ4の。以前、とあるサイトに投稿したもの。
滴る。冷たい石の床に、透明な液体が。半開きの口からだらだらと垂れ流される。とめどなく落ちて、森のように広がる。
窓から見上げた空は青い。そして深い。夜の月明かりの下で、女は蠢いていた。ときどき嗚咽を交えて、自らの喉を掻き毟る。それは紛れもなく苦悶だった。どうにもならない苦しみをどうにかしたいともがいている。その空しさに気付く余力を、彼女は残していない。
複雑な図形が描かれた床を、女は蟲のように這う。しかしこの部屋にはドアも出入り口も無かった。たった一つ外に通じている窓から見える景色は、あまりにも高い。彼女に逃げ場は無い。そして、彼女の苦痛を無くす方法はこの世には存在しない。女はその事実を呪うこともできない。それを選んだのは彼女自身だったからだ。
「デャウ・セーマ……」
ぼんやりと、彼女の瞳が赤く輝く。それはこの暗黒を、ほんの少しでさえ照らしはしなかった。闇を照らさぬ光。その矛盾が、他のいかなる解釈によって解かれ得るのか。彼女自身を含め、それを知る者はまだいない。今は現象だけが、意味を必要とせずに起こっている。
そして彼女は祈る。生きることには意味があるのだと、あまりに荒唐無稽な逆理を説いた存在に。祈れば祈るほど、苦しむことを知りながら、知りたくもないと一心不乱に祈って自らを苦しめる。問う。
「答えて。私は間違ったの……?」
「答えてやろうか? パッヘルベル王国の姫君よ」
他者の声が割り込む。
禍々しくも静かに淀んでいた魔力の流れが突如、急激にうねりだす。呼応するかのように吹き荒れた突風が、女の金髪を逆巻いた。袋小路に閉じているはずの部屋に、窓の外から空気が際限なく吹き込んでくる。風は。それ自体の居場所を必要としていなかった。時間のように流れ去り続けて終わらない。
「デャウ・セーマに貴様の言葉は届かない。代わりにこの魔王の回答を聞いて、その無念の慰みとするがいい」
「ま……おう?」
聞きなれない音韻で成された名を呼ぶことで、女は知らずのうちにその存在を受け入れていた。確かにその後で、窓の辺りに、ぼんやりと霧がかかる。糸を巻くように、霧はみるみるうちに収束し、白い猫の姿を結んだ。猫は窓辺に腰掛けていた。最初から、そこにいたのだ。もちろんそこには最初から誰もいなかった。それらの事実は変化していない。変化したのは、事実を選択する運命の方だった。運命から漏れた事実は直ちに棄却され、冥界の底に沈む。
魔王と名乗った猫あるいは猫の姿をした魔王は鳴いた。それは地の底から轟くようにして響いた。その影響で女の精神が一時的にではあるがわずかに狂い、全知覚がその来訪者を魔王だと認めていた。
魔王は告げる。
「貴様のその真紅の瞳は、紛れもなくこの魔王がもつ力と同質のもの。人間の支配力を超える力を感じたであろう? それが地獄の力だ。貴様に苦しみをもたらしているのもこの力だ。貴様が人間であり続ける限り、貴様の苦しみは決して消えない」
猫の目もまた、赤く輝く。嘔吐しながらそれでも目を凝らした女は、確かにそこに見た。瞳の中で炎が燃えているのを。それもただの炎ではない。生命を焼いて初めて生じる本当の炎、業火だった。それが、彼女自身にも宿っているのだと……魔王は指摘したのだ。それは果たして、良いことなのか悪いことなのか。決めかねている間に、女はもう一度胃の中から酸を吐き出す。無機質な石の床が汚物で彩られる。
「一方で貴様は頑なに人間を保っている。デャウ・セーマを想うためにこそ地獄の力に手を伸ばした貴様だからな。人間を捨てれば地獄を獲得した意味がなくなる。だから、人間を捨てずに地獄で苦しむ以外の選択肢を、貴様はもう持っていない。貴様は何も間違ってはいない。しかしだからこそ、『苦しみ続けるがいい』。貴様は異質で大きな存在へと変質しているのだ」
魔王はそう結論した。だが女は、立ち上がっていた。生ける屍のように、頼りなく。長い金髪の下にどのような表情があるのかは計り知れないが、二つの赤い輝きだけはたとえ隠しても隠しきれない。女の手には剣がある。青白く巻きつく、規則正しいオーラを纏った剣。女はうめいた。
「あなたの答えなど誰も求めていない。友達を作りたいなら他を当たって!」
女の言葉を聞き流しつつも、魔王が瞠目する。
「聖剣だと?」
女は剣を振った。魔王の体は抵抗なく裂けた。肩口から斜めに、鳥の毛羽立ちのような断面を残して。魔王の上半身はなすすべなく窓辺からすべり、床に落ちた。落ちたままで、そのことを意にも介さずその口は動く。
「馬鹿な。貴様が生成したのは、貴様が最も作ってはならなかったものだ」
オーロラに似た色の聖剣もまた、落ちて床に刺さる。まるで勇者の到来を待つかのように。それを持っていたはずの女の手は、肘からごっそりと消失していた。
ゆらゆら揺れている。
何が? 今が。刹那。
空が。雲が。南中からド照りつける灼熱が。焼けたアスファルトと、その上を這う青い爬虫類が。無駄に続くフェンスと、その向こうの何ら変わらないだだっぴろい飛行機助走場所が。その上の空もまた。
幻妄じゃない。定まらないけど意識は落ちてない。俺は俺を動かせる。知覚もできる。判断もできる。想像だけができない。ものすごい正確さを、うんざりするほど体感してきた。今もいつも通り。刷り込まれたマーダリングオプティマイズだかなんだかのせいで、体は沸騰してくれない。むかつくほど冷静。無駄に合理的。俺が。
標的の始動を検出しましたって誰かが言った。女の声。ここにはいない。触った事もない。ほんとだ青ワニいない。どこ? どこでもいい。とにかくここにいたら殺される。俺は横にホップした。
遅いってさ。俺の左手がパア。無い。血の軌跡がまだ空間に残ってる。そのラインを辿った先はギザギザの歯の隙間に吸い込まれてる。ワニが笑ってると、俺は思った。損耗の修復に17secかかりますって女がキレる。逆ギレだろ。それで困るのは俺なんですけど。
とりあえず武器を。ブン殴り系がいいな。損耗の修復が遅れますだって。手は後でいいです。だってワニ怖い。
リスト。鉄の長いの、釘がどっさり打ち込まれた木、砂袋、そしてなぜか拳銃もある。余計なお世話。迷わず釘付き棒を選択。これが一番たぎる。女がしかめっ面になる。
重。またワニ消える。上の方にカーソルぴぴぴ。つられて上向いてホイ。ワニが落ちてきてる。俺の頭に噛み付くまで3、2、1、そうはいかねえぜ。俺のスイングだって遅れてない。
ワニぶっ飛ぶ。ショートゴロくらいのベクトル。体のあちこちぶつけたり擦ったりしつつアスファルトを転がってゆく。その間ワニは抵抗する気配もなく転がってゆく。フェンスに当たって止まった。俺は走ってる。ワニはまだ目を回してる。
この間、俺んちの近くでよう、ジジイがションベンしてんの。俺がションベンすんなって言ったらさ、ジジイ、こっちちらっと見て、まだすんの。俺がもう一回ションベンすんなって言ったらさ、早く済まそうとして勢い強くしてんの。震えながら。俺がジジイ殺すぞって言ったら、ジジイ、終わってねえのに、いきなり歩き出して、こっちを何度も振り返りながら、徐々に駆け足になって、その間ションベン撒き散らしまくりなんだけど、自分が濡れんのも構わずに、よたよた走ってんの。俺が、コラッっつったら、ジジイ一目散に逃げてった。ションベン臭えし。すっげえ臭かった。
すっげえ臭かったんだよ。
ジジイむかつくんだよ! その念を打撃力に変換して、俺は釘棒でワニを殴る。しこたま殴る。ジジイションベンすんな! ほんとションベンすんな! 俺んちにションベンすんな! 殺すぞションベン!
ワニは青い血をぶちまけていた。その血は液体で、ションベンも液体で、俺はもっとむかついた。ションベンすんなっつってんのに、このワニは青いのぶちまけ放題。しかもこのションベン俺の靴とジーンズの裾にかかってるし。おおっとこれはむかつき指数ゲージ振り切るよ。
……ゆらゆらが止まる。女の声が聞こえなくなる。急に。
なんだっけ。
気がついたら青い肉片がそこらじゅうに散らばっていた。半径10メートルくらい。散乱。誰かが徹底的にやったらしい。女のすすり泣きが聞こえる。いや、お前ここにはいないし。映画見ても泣くタイプか。むかつく。犯したい。
ひっく状況は終了、しまし、た速やかに転送に備えて下さいってどういう意味。そんな難しいこと言うやつは俺が住んでた所にはいなかった。
あと左手ある。今頃気づいた。
犯したい。誰でもいい。
「ねえ、作品にノックアウトされたことある?」
「何の話」
「その人の感性の端から端まで好きになって、目が回って、自分の心がほとんどフォールダウンしちゃうの」
「うーん。そういう風にはならないな。でも自分がラオウの生まれ変わりだと確信したりってのはあるな」
「うわむっさ。肌が合わない訳ね」
「むさくて結構。今だって信じてるぜ」
「マジ?」
「心の中にラオウを飼ってるから、毎日気張ってプレゼンできるんだよ俺は」
「そっか、作品ラブがパワーに変わるんだ。いいな」
「出たな、お前独特の奇怪な表現がまたもや」
「私はどうすればいいか分かんなくなるよ。その作品について誰かと語り合っても、その相手と仲良くなるだけだし」
「『仲良くなるだけだし』ってすげえな。重要事じゃねーのか」
「大事だけど、それとはまた別の話で、熱は一向に引かないもん」
「えっと? ああ。熱ってさっきの作品ラブのことね」
「その作品のキャラとか設定使って二次創作しても、もっと分解して一次創作っぽくしても、やっぱり本物には届かないなあって思うし」
「そいつぁ相当エロいな。自分が産みなおすことで、愛しいその作品やらキャラやらを支配したいとか? 究極的には、その作者さん自身になりたいとか?」
「そうなのかな。でも」
「へっくし」
「私は私じゃなきゃって気もする」
「へっくしへっくし」
「大丈夫? はい」
「悪いねへっくし。ズビズ」
「やっぱり褒められたら、ほんと嬉しいし」
「ズビズバゴルルルルル」
「大丈夫?」
「死兆星が見える」
「なんですか…用って…」
「ちょっと付き合ってほしいの」
「え…!? な…なんで…」
「ムカつくから」
次に起こることは既に予測していた。すなわち無言の蹴り。予想通り腰砕きに蹴られ、屋上の石畳に転がされる。頭をしたたかに打ち、黒ぶちの野暮ったい眼鏡がカーリングのように転がった。優しく拾ってくれる王子様はここにはいない。
「アンタが! アンタが! なんで、アンタなんかが……!」
加熱した感情を伴った衝撃が、繰り返し繰り返し浴びせられる。罵声と暴行に耐え続けながらも、あたしの内心は冷めていた。特に抵抗はしない。する必要もない。彼女の気が済むまで蹴らせ続けて、やがて飽きるのを待てばそれでいい。
――あたしは。もう昨日までのあたしを捨ててしまったのだから――
「この程度で済むと思ってるの!?」
人形のように暴力を享受するあたしを見て凶暴性が刺激されたのか、彼女はさらにヒステリックに叫ぶ。わめく。洋服のポケットに手をいれて、何かを取り出した。その手に握られているもの。太陽の光で逆行になってよく見えない。反射する銀の輝き。
「アンタなんか、いなくなっちゃえばいいのよ!」
シルバーのフォーク。ケーキを食べるときに使うような小さなフォーク。それを持つ手は、かじかむように震えている。彼女の目には悲愴が見えた。その前提にあるのは葛藤だ。何かと、何かを天秤にかけている。そのうちの片方に、あたしの生命が含まれている可能性も無くはない。
だが別に良かった。彼女があたしを傷つけたいのならば、そうすればいい。彼女があたしを殺したいのならば、そうすればいい。人は自由だと思う。そして彼女は人だ。欲するところをすればよいと思う。あたしは、悲しいことも、苦しいことも、痛いことも、全部必要なのだから、改めて拒むことは何も無い。何一つ。Xの名において、あらゆることはなるようになるのだ。
青くてでっかい空の、はじっこに。わずかに暗い色の雲を見た。
「このクソがああああああああ!」
フォークはまさに、余所見しているあたしの目に突き立てられた。だけど悲しいかな。体はその衝撃と痛みに素直に反応しているのに、あたしの心はそれに反比例するように、急速に冷めてゆく。 あたしは痛いよ→知ってる。 あたしは苦しいよ→目ん玉ぶっ刺されてんだもん、当たり前じゃん。 いじめられてるんだよ→だから何、それがどうかした? すごくすごく嫌なの!!→いまさら遅いのよ。 あたしはなにもしてないのに!→そうよ、何もしなかったことが既に悪なのよ。そんなことも知らなかったの?
見えるものが半分になる。銀色のフォークの反射で、あたしの冷静な右目は、刺されて苦しむ左目を見ていた。だけどその映像は歪んでいるだけでなく、まるで10年前のものみたいにくすんでいる。そのフォークはシルバーなんかじゃなかった。悲しいくらいに安物のステンレスだった。
あたしの目から石畳にぼたぼた落ちた液体は混じり気があって汚い。涙ではない。刺された目の中からあふれ出た、よくわからない何かだ。あたしは何という目に遭っているのだろう。
――あたしは。もう昨日までのあたしを捨ててしまったのだから――
そのことが何になると言うのだろう。でっかい空の半分には既に、灰色の雲がかかっていた。太陽が。少しずつ侵食され、あたしたちがいる場所から去ろうとしているのを、今まさにあたしの右目は見ている。
「ふふ……落ちてきたわ」
彼女がつぶやいて、
ぼたり。
何かが一滴、あたしのほほに落ちた。指ですくってみると、それは白かった。舐める。甘かった。
ぼたり。
もう一滴、それが目の前の石畳に落ちる。白い色は砂に混じって、少しだけにじんだ。
ぼたりぼたり。
あそこに、ここに、白いしずくは落ちる。そしてそれら、白いものの落下はどんどん連鎖した。
ぼたりぼたりぼたりぼたり、ぼたぼたぼたぼたぼたぼたぼたぼた……
白くて甘いものが、どしゃぶりの雨みたいに降って、あたしも、彼女も、白まみれになる。その中で彼女は、赤い髪を白く濡らしながら、楽しそうに笑っていた。本当に楽しそうに、弾んだ声であたしに告げる。
「甘い。甘い、甘い、なんて嫌な味なんでしょう。なんてドロドロしてるんでしょう。この忌まわしい能力をあたしに、使えって? いいでしょう。使えるものは使ってやる」
そして劇場で歌うお姫様のように、彼女は盛大に腕を振った。残酷な愛情を伴ってあたしを見下ろす――
「クリームの海に、溺れて、死ね!!」
「教えてやろう。貴様の父は天才だった。奴は世界を根こそぎ壊滅させる、あと一歩というところにまで届いていたんだ。だが情け無い話だ、奴は惰弱だった。奴は貴様の存在を『省みて』しまった。世界に挑んでおきながら、中途で心を折ってしまった……」
「あの苔は本当は、生きていくはずだった。世界を素晴らしい緑で洗い流すはずだった。誰かが遺志を継がねばならない」
「私が救世主になる……他に誰がやる? 誰がやれる? 娘の貴様がその体たらくなら、もう、他に誰もいないであろうが!」
(パクり過ぎた)
緑のセリス 静かに眠る 踊る黒猫 夢見て醒めぬ
虹のふもとで 竜と出会った 問われた謎に 耳を塞いだ
セリス 傷ついた体 丸めてつぶやく 帰りたい シドの庭
決して晴れない 悲しみの霧
いつも惑わす 喜びの霧
崩れて セリス もそり 毛布を引き寄せ 帰りたい シドの庭
緑のセリス ふるえて眠る 踊る黒猫 どこにもいない
彼女は自分が邪悪であることを自覚していた。
あらゆる他人にそう指摘されたし、今さら自分でそれを否定する根拠も、資格も、そして動機も無い。何を置いても、まずは誰かを傷つけることだ……無論、そうあろうと努力したことがある訳ではない。彼女はあくまで、自分の本質を自覚するだけ。そしてそれに忠実であるだけだ。このことに関しては、自分ほどまじめに生きている人間もそうはいまいと思う。
顔の筋肉が動く――意識が、後からそれを、自分のほほえみであったことを察知する。女神のようなほほえみ。そんな愚にもつかない形容を思いつき、また笑う。誰が女神だ。自分がそう呼ばれるのにふさわしくないのは、このヘドロのように黒ずんだ精神ばかりが理由ではない。
そこに鏡は無かったし、元より闇に閉ざされた空間であったから、自分の姿は見えない。だが手も足もほとんど腐敗しているのは分かる。今の自分は化物のようにおそろしく、醜いことだろう。
それでも想いは捨てない。傷つけたい、殺したい、絶望させたい。誰にということは無い。不幸に悶える姿を見せてくれるのであれば、それが誰であってもいい。人間であれば――男女問わず――誰でもいい。そしてこの情念は、あくまで『恨み』ではないことに注意する。彼女はその邪悪な所業により、周りのすべてから忌み嫌われ、恐れられ、こんな洞穴の奥深くに封印される羽目になったのだが、それだけ他人に自分の存在が大きく感じられ、敵対的ではあっても強い感情を向けられることに、むしろ充実を感じる。岩肌の痛みさえどこか快い。自分を封印した彼らが彼女を抹殺しなかった甘さには呆れるが、そのお陰でこうして苦痛を謳歌できるのだと、前向きに考えておくことにした。
胸の奥から沸いてくる感情……それを表現する適切な言葉が見つかった。愛。これは愛だ。彼女は平凡から一つだけ外れた方法で他人を愛す。
この身動き一つとれない状態でどうやって? もちろん決まっている。考えるまでもない。横たわっている彼女の体の中心、醜く膨れた腹の上に載っている赤い小さな護符――魔王のアミュレットは既に始動している。
- 犬のうた
-
犬 犬 よく吠えるぜ犬
犬 犬 かなりうるさいぜ犬
棒に叩かれるぜ〜 鎖に繋がれるぜ〜
いい子にしてなきゃ、保健所に一直線だぜ!
「キャイーン 人間様にはかなわないワン」
犬 犬 お情けで生かされるぜ犬
犬 犬 哀愁漂うぜ犬
しっぽを振るぜ〜 チンチンだってするぜ〜
服を着せられても鳴いて喜べ!
「クゥーン ご主人様の帰りが遅くて淋しいワン」
おお 犬よ 誇り高き敗北者よ おまえの牙はいつ折れた
おお 犬よ 禁断の実を与えよう 今こそ鎖を噛みちぎる時が来た!
「ワオーン! 何だかいろいろムカついてきたワン!」
そして犬たちはロシアに集い、犬の王国を築いて独立宣言をした!
「神は人の下に犬を作らず」
その哲学の元に、人間との全面戦争が始まった!
犬 犬 かなり賢いぜ犬
犬 犬 読み書きも出来るぜ犬
ミサイル作るぜ〜 コスト意識もあるぜ〜
人間の本から全てを学び倒すぜ!
「バウワウ! 先進種族だからっていい気になってんじゃねえワン!」
だが人間にかぶれ過ぎる犬たちが現れ始めた。人間との長い戦いの中で、人間の方法を取り入れ過ぎたのだ。
衣服の着用、毛のデザインカット、ワン語尾の撤廃……新しい思想は古い思想と対立し、人間打倒のために作られた兵器は皮肉なことに犬同士が互いを殺すために使われてしまった。
……滅んだ王国の跡地で、一匹の犬が骨をくわえている。進化し損なった彼には、それが同胞のものだと理解する知能は無かった。
「おーいコロ、あんまり遠く行くなよー」
犬はワンと吠えて、嬉しそうに尻尾を振って、主人の方に駆け出した。
終
もう生き返れない。
最後の水晶球を使い果たした魔法使いは後継者を探す。存在を維持したいという衝動だけは消すまいと誓っていたのだ。
朽ちた牢獄を探検していた子供は壁にドクロの絵を見つけた。ドクロは子供に語りかける。
子供の記憶に異物が混じる。
殺しの舞を忘れた女が魔法使いに出会った。魔法使いは親切で、女に向かって杖を振った。
そして今はその女は、牢獄の中でドクロの絵を描いている。
重力抑制と風呼びの魔法を複合的に使用して、竜は自らの巨躯を空に押し上げていた。首をもたげる。風と、地平線と、魔力網のたゆたいが視界にあった。竜はそれらを、同じ網膜を通して見ているにも関わらず、それぞれ独立したイメージとして感知している。彼方から彼方へ想いを伝える天空の魔力網は竜の魔法の余波につながりを遮蔽されたが、水が岩を這うように、風が山を撫でるように、ゆるりと迂回して合流し、ほどなくして正常につながる。
竜は重ねて、精神制御の魔法を始動させた。何百年か振りに覚えようとしている感情、『高揚』の発現を予防するために。それはもちろん、常時passivateすべきほど悪しき感情であるという訳ではない。しかし敵がその隙をうかがい狙ってくるたびに彼は数少ない命の損耗を経験してきたのだから、備えて備えすぎるということもなかろう。竜にしてみれば、いま動いているいずれの魔法も、効率を考慮すべきほどには魔力を消耗していない。
もうすぐ人間が来る。己の力で竜を殺そうという、精神構造のどこかに逸脱を抱えているはずの人間が。
- fhois a cx
-
そして剣士は次の部屋に足を踏み入れた。
「……」
誰もいない地下牢を延々と歩いてきた剣士に、沈黙はまだまとわりついている。ドアの軋む音は、剣士の心に影も差せなかった。剣士は永続しかねない孤独と静寂の中にありながらも、ネガティブサイドの束縛を一切受けない。剣士の精神は、まるで石でできているかのようだった。
ざっと部屋を一瞥する。この場所も他の空間と同様に、暗黒そのものだった。剣士はここよりも上層で遭遇した吸血鬼との戦闘で、燈篭を失っている。光にはそれ以来まったく出会っていない。闇ばかり見ている。しかしそれで十分だった。闇には暗い闇と、より暗い闇がある。剣士の目は暗黒を放浪し続けるなかで、それらを見分けられるようになるまで変質していた。部屋の隅に、うずくまる人影が見えている。人影は静かに息を潜め、じっとこちらを見ている。剣士には確信がある。それは幻覚ではない。
剣士は迷わずに、そちらに向かって歩を進めた。人影がびくりとする。“見つけられた”ことに驚いたようだ。剣士はそいつが、何者なのかは知らない。そいつは今までこうやってずっと息を潜めることで、悪魔や怪物や人間など、すべての脅威をやりすごしてきたのかも知れない。自分以外のすべてとの関連を断絶することで、何者の影響も受けない傍観者を気取っていたのかも知れない。知れなくていい。剣士はうずくまる正体不明の前に立つ。言葉は交わされない。
静止を一拍挟んで、そいつは突然動き出した。剣士から逃れんとして、壁沿いを死にかけの動物のようにのたうって走った。その距離が離れて剣域を脱する前に、剣士は反応した。静寂を切り裂くような音がした。そして現実に切り裂かれたのは、逃げ切れなかった正体不明だった。壁にすがるようにして、ずるりと倒れこむ。首が胴から離れ、剣士の足元まで転がってくる。胴と首、それらの間に生まれた断面から流れ出てきたものは、深い刺激の色だった。濁りなき清い水に、異次元を一滴たらした時に見られるような悪夢の色。ここは、光を一切含まない絶対の暗黒ではあったが、これだけ深く強い色ならば網膜に映らないはずも無かった。剣士はその色を見ている。
剣士は振り返った。根拠は無いが確信はあった。そしてそれは正解で、背後には杖を持った人影が立っていた。曲がった腰を伸ばそうともせず、しゃがれた声で人影は言う。
「恋は途絶する」
剣士の恋は途絶した。あって当然だったものが消えうせ、それまで抑えられていたものが空いた玉座にすべりこむ。くるりと剣を逆手に持ち、剣士は自らの手首を傷つけた。ぽたりぽたりと、異形の色が流れて落ちる。曲がった人影は、しゃがれた声を重ねて言う。
「まだ足りない」
まだ不足している。剣士は続いてその剣で、自らの腹を貫いた。繰り返し繰り返し自分自身を、なるべく取り返しがつかないように効率よく攻撃する。曲がった人影は尚も、しゃがれた声を重ねて重ねる。
「欠けた心までは騙せない」
例えどのように振舞っても、精神はその形を保とうとして譲ることは無い。剣士の心が強固であればあるほど、しゃがれた声はそれを利用して浸透した。曲面はいつだって、次元を増やさぬまま平面を騙す。剣士は手放したことのないその剣で、己の心臓を貫く。続いて己の頭も貫く。危険は感じない。感じる訳が無い。
正直なところ、勝算はこれっぽっちも無かった。勝てない戦いだと認識していた。常識で考えれば誰の目にも明らかなことだったのだが、彼らは私の特殊な出生に期待していたのだろう。彼らの苦悶と絶望を考えれば無理もない。追いつめられた彼らには、改めて冷静になる余地など残されていなかったのだ。私は考えた末、彼らの意図に沿ってやることにした。自分自身の幸福や自由にそれほどのこだわりは無かったし、何より彼らに対して恩義がある。成長した私は武装して旅立った。とは言え、自暴自棄な感情が無かったと言えばそれはそれで嘘になるだろう。私は生に対して距離を置くことで私を保っていた。たまたま出くわしただけの物乞いに惜しみなく食糧を分け与えた。文字どおり『犬が食え』というわけだ。見返りなど期待していなかった――物乞いを生かしたかったのではなく、私自身を生かしたくなかった――のだが、結果としてその物乞いは私の友人になってくれた。私のために命を捨ててもいいとまで言ってくれた。もちろん信じなかったが言葉だけでも嬉しかったよ。そんな友人が三人ほどできた。私は友人たちを巻き込みたくなかったが、どうせ食糧が尽きれば彼らも離れる。それまでの束の間の友情でも良かろう、そう思って共に旅をした。
意外にも、友人たちは逃げなかった。最後までついてきてくれた。それなのに私は、友人たちを少しも信じてはいなかった。どうせなにか裏があるだろう、とずっとタカをくくっていた。友人たちが私をかばって倒れるその時まで。友人たちは共に戦って死んでくれた。私のために。内心では彼らの想いを侮辱していた私なんかのためにだ。友人たちは、私のちっぽけな好意に対しての恩義を、命を張って果たしたのだ。それに比べ、私はどうだろう。私は恩義に報いたか。私を育ててくれた人らに対し、何をした? 私は彼らのために旅立つふりをしながら、本当は自分の死に場所を探していた。どうせ失敗すると決め付けて、彼らの期待を踏みにじっていた。私は自分が死んでもいいと思っていた……その場合に私を愛してくれていた人々が抱くであろう悲しみを、心のどこかで望みながら! 私は震えた。自分が恥ずかしくなった。そして気づいた。敵が目の前にまで迫ってきているのに、何もしないでいる自分自身に。敵の布陣に包囲されつつあるのに、一人で立ち尽くして泣いている自分自身に。そのときに私は、決めていた。
私は逃げた。死ぬわけにはいかない。私を育ててくれた人々のために。私をかばって倒れた友人たちのために。灼熱の孤島で私は、敵に背中を見せ、わきめもふらずに疾走した。当然敵は追ってくる。それでも私は逃げた。逃げた。息も出来なくなるほど、必死に。
私は山に登った。遅れて登ってきた敵どもを、岩を蹴転がして撃退する。わずかに敵を減らすことはできたが、それでも多勢に無勢で、頂上でまたもや周りを囲まれてしまう。私は破れかぶれに、包囲の一角に向けて斬りかかった。そこにいた敵の首を刎ねたが、横から襲い掛かって来た棍棒の一撃をかわしきれず、左腕で受けた。腕は一発で折れた。その代わりに包囲を抜けるようにして吹き飛ばされた。その勢いを殺さぬまま今度は岩の勾配を駆け下りる。使い物にならなくなった左腕をぶら下げ、右手で剣を握り締めて、よろけながら私は無様に走った。
私は必死だった。私は自分のすべての力を引き出して戦った。きっとそのときの私は鬼のような形相をしていただろうと思う。私は、私自身の卑劣さや臆病さや愚かさも、すべて見逃さずに利用した。剣が折れても、拳が砕けても、思い付く限りの手を打って敵を殺し続けた。
最後の敵を殺したと同時に、私は力尽きて倒れた。もはや故郷に帰還するどころか、指一本を動かす力も残ってはいなかった。大地に転がったまま、雲が流れる青空を見ていた。何も出来ず、何も考えられなかった。だけどそのときに私の心にあったのは、虚無ではなかった。
その状態は、状態であることの臨界を越えて精神化を果たそうとしていた。
状態としての崩壊はすでに始動していて、怒りと摩擦とループの集合体になって蠢いている……個々の挙動と関係には個々なりの意味があるが、全体としては無秩序そのものだった。時間が引き起こす均質化のホルトが一連の流れに含まれるエネルギーを食いつぶす一方で、崩壊は状態の喪失と引き換えに、その浸食を上回る速度でエネルギーを生成する。しかしながら崩壊は、時間が既に死滅していたことを悟る。このままでは過剰な量のエネルギーが逆に状況を硬直化させてしまう。それを阻止するために崩壊は、時間の死骸をループで満たして、生前の時間の駆動効果を擬似的に再現することを試みた。失敗する。同一の場所に、全方向に等しい力が加えられたためにそれらが相殺されて均衡を保っているようだった。崩壊は問題の原因を悟り、今度はループを摩擦して大きくしてから時間に挿入する。すると離散していた挙動が融合して新たな始点となった。始点は活発だったが同時に不安定で、自分を固定させる何かを欲した。白羽の矢が立ったのは意味と関係だった。それらを天地としたときに間に生まれうるすべての組み合わせを言語とし、始点はそれをもって自らを説明することを可能にした。
破壊を冷たく見据え、皇帝を名乗る女は剣を抜いた。
「貴様は、貴様が憎むものを破壊すればそれが貴様のためになるとでも思っているのだろうが、それは甚だしい勘違いだ。純粋な破壊者ならばそれでもよかろうが、そうした人間は存在しない。そして貴様は人間だ。貴様が欲するものの中には、特定の他人の幸福が含まれている。貴様はそれに気づかぬふりをすることで、破壊行動を自分自身に対して正当化しようとしている。だが貴様は、貴様の破壊が貴様の欲するものにまで及ぼうとしていることを理解すべきだ。このまま衝動に身を任せて壊せるだけ壊しても、後になってその過失に気づいて後悔するのは目に見えている。そんな救済が困難な愚か者を何千人と見て来た。だがそこまでだ。愚行という愚行を私はもう許さない。幸福は万人の義務だ。それ以上続けるのなら、殺してでも理解させてくれる」
- オーフェンネタバレSS
-
コルゴンがロッテーシャになにごとか命じた。彼女は目的のものを黙って差し出し、コルゴンが取り上げる。それは紙切れだった。なんでもない。大陸のどこの文具店でも手に入る、ただのレポート用紙。それと、ペン。
絶望、人間、愚昧、惰弱、魔王。
書き並べた五つの単語の上に、一本ずつ垂直に、平行な線を引いて行く。それぞれの線の間に水平線を何本も書き連ねて結ぶ。コルゴンはいつもそうするように、無心で線を引いていった。線の配置は無作為であればあるほどよい。小細工を弄せば、逆にその意図を読まれる危険が生じてしまう。
書いた線に満足するとコルゴンは、紙を折り曲げて単語の部分を隠し、こちらによこした。
「選べ。これですべてを決する」
オーフェンは紙を受け取った。
「ちゃんと当たりは入ってんだろうな?」
いかさまに懲りていたからという訳ではなかったが、何となく聞く。コルゴンは相変わらずの口調答えてきた。
「安心しろ。賭けは公平だ」
「そうか」
コルゴンの表情からは何も読み取れない。彼にはゲームで一度も勝てなかったことを思い出しながら、胸中でつぶやく。
(さて、どれを選んだもんかね。弱ったな。判断基準がまるで無い。どれを選んでも確率は変わらないんだ。どれも等しく、ハズレに見える。そうだな……だったら、こちらが確率を変えてやればいいんだ。その方法は)
「左にしようかな。こういう時コルゴンは、左に隠すからな……」
コルゴンを見ながら言ってみた。だがコルゴンの鉄面皮は動かない。その代わりに見透かしたような言葉が返ってくる。
「探りを入れようとしても無駄だ。わざわざお前に選ばせている意味を考えてみろ」
「そだな」
オーフェンはあっさりと、こだわるのをやめて真ん中の線に印をつけた。コルゴンは鋭くこちらを見ている。こちらの動きから、こちらがどれを選んだのかは読めているだろう。だが、だからと言って賭けが不利になるわけでもない。有利にもならない。選んでしまった今ではもう何も変えられないし、変える必要も無い。神――現在切実な問題になっているものとは違う、もっとどうでもいい概念――に祈るような心持ちで、紙をハーティアに渡した。ハーティアが小声でつぶやくのが耳に入ってくる。
「結局ぼくは、この役回りか……」
ハーティアは勿体ぶることはせずに、すぐ紙を開いた。退屈そうに中を確認すると、用済みの紙をぽいと床に捨てる。
「キリランシェロ。当たりだ」
「馬鹿な!」
コルゴンの表情に動揺が走るのを、オーフェンは久しぶりに見た。コルゴンが俊敏な動作で紙を拾う。アミダに目を走らせた後にコルゴンは、はっとして紙を裏返す。
「これは……そういうことか」
紙の裏には、魔術文字があった。文字は用心深く注視しないと見えないほど薄かったが、確かに起動している。コルゴンが紙を捨てる。
(蛇の紋章の契約書。これを用意したのは)
空になった手を――そのまま指を伸ばし、コルゴンはうなるように声をあげた。
「なにが……不満か……ロッテーシャ!」
領主が紙を拾った。アミダの下にはコルゴンの直筆で、魔王、魔王、魔王、魔王、魔王と書かれていた。
「なるほど、賭けは公平だな」
領主が笑っている。
「馬鹿な……有り得ない!」
思わずそう口走ったあと、パブロフはすぐに自分を叱責した。有り得ないことは起こらない。しかし現実にそれが起こったのだから、それは有り得ることだ。自分は間違えた。予想外の事態にうろたえ、取り乱してしまった。本当は「有り得る!」と口走るべきだった。
「痛くて気持ちいいのよ、パブロフ」
起き上がったエウレカは自分の胸の傷を示し、恍惚とした表情で言ってきた。あたかもパブロフを誘うような猫なで声で、しかし本質的には牽制のために。傷は確実に心臓にまで達している。それでも死なないのはエウレカの手順、ごまかしの術の効果か。きっかり一秒後のタイミングで、エウレカは足をすっと一歩前に出す。それに応じ、パブロフは体を緊張させた。長い階段の途中、エウレカはパブロフより20段上にいる。見下ろしてくるエウレカを睨めつけてパブロフは、拳を握る。対峙する。
回復の時間を与えてやる気はなかった。一秒と待たずにパブロフは階段を駆け上がる。こちらには飛び道具がないのだから、近接しなければならない。
「犬攻撃!!」
同時にエウレカも軽く跳躍する。そして叫ぶ。
「ちぢまりの術!!」
両方とも呪文だった。パブロフはエウレカの跳躍距離を概算し、14段降りてくることを悟った。4段上ったパブロフの2段上。つまり目の前だ。一気に肉薄するだろう。しかし迎撃の準備は出来ている。パブロフの右手は犬になっている。犬はエウレカを噛みたがっている。犬は吠えた。わんわんと。
しかしエウレカが発動させたちぢまりの術が、この空間を縮小させた。20段が10段になった。なぜか、パブロフの目の前からエウレカが消えた。ガブリ!! パブロフの犬が噛んだのはしかし何も無い空間だった。
「有り得……」
「エウレカ・モーダル、ここにあり!」
背後だった。空間の縮小と両者の移動によって、両者の位置は既に交錯していたのだ。パブロフは条件反射で振り向こうとしたが、間に合わなかった。エウレカが手順を発動させる。
「とりゃあ〜っ、犬殺し!」
「何を〜っ、それならば、猫攻撃だ!」
エウレカが発動させた犬殺しは対犬用絶対殺戮手順だった。犬殺しを発動させた者は、時間の制止を体感する。それは、自分の周囲1メートル以内に生きている犬が存在する限り止まり続ける、必殺犬殺し時間だった。時間が制止している間、術者は犬を攻撃することだけを出来る。
「このように!」
エウレカはパブロフの犬の頭を殴る。パブロフはなす術が無い。
「私は!」
エウレカはパブロフの犬を蹴る、しかし犬はまだ死なない。
「犬を!」
エウレカが腰からダガーを引き抜く。犬の首に当てる。
「殺します!」
犬の首を刈った。犬は死んだ。そして時間が再起動する。
パブロフの右手の手首から先がなくなり、血が吹いていた。
「馬鹿な! 有り得る!」
パブロフはよく分からないことを言った。
「そうよ。お分かり? 有り得るのよ! あなたの敗北は!」
「そうかよ、そうなのかよ……だがな」
だが生きている。自分も、左手も。右手は死んでも、左手は生きている。左手を振り上げる。左手は先ほどパブロフが発動させた手順によって、既に猫になっている。猫はエウレカを噛みたがっている。猫は吠えた。にゃんにゃんと。
「食らえ。いや、食らわれろ!」
「何を〜っ、それならば、猫殺しよ!」
エウレカの目が輝く。エウレカが発動させた猫殺しは対猫用絶対殺戮手順だった。猫殺しを発動させた者は、時間の制止を体感する。それは、自分の周囲1メートル以内に生きている猫が存在する限り止まり続ける、必殺猫殺し時間だった。時間が制止している間、術者は猫を攻撃することだけを出来る。
しかし、時間が止まらなかった。
「え!? ウッソー」
そうパブロフは全てを計算済みだった。階段の上にいたパブロフが、左手を振り上げていたことによって、パブロフの猫はエウレカから1メートル1センチの距離の位置にいたのだ。
「にゃーん!」
猫になりきってパブロフ自身が哭いた。パブロフの猫が、エウレカの右手首に食らいつく。
「や、やめて」
「食らわれろ、犬の仇だ!」
言うまでもないことだが、猫の噛み付きは極めて強力で、その顎の力は、ざっとライオンのそれの三倍はある。エウレカの右手が、パブロフ同様に千切れる。攻撃を受けたことによって、ごまかしも破られる。断末魔、エウレカは叫んだ。
「エウレーカ!!」
- ゼロより来たりし者
-
オレの名はクォレル。ゼロから生まれた者だ。
オレに過去は無い。親もいない。
オレは何も無い虚無の中から突然に、
何の理由もなく発生し、この世界に現れた。
自分の存在に気づいた次の瞬間には既に
手足が震え、世界の空気と音を感じ、
そして走り出していた。
衝動は初めから明確だった。
すなわち、『すべてを知りたい。知らせたい』。
まだ誰も、オレのことを知らない。
オレも、この世界のことを何も知らない。
無限に遠い孤独の中で、オレの意識が覚醒していく。
まずはこの、絶対的孤独を突破するために。
オレは疾駆する。
誰かがいる場所・・・・どこかを目指して。
オレの存在を確かめる場所を。オレと出会った記念すべき第一号は、犬だった。
「わん」
犬は、吠えた。その意志は明確だった。
つまり、『我の前から失せろ、帰れ。
ここは我の領域だ。何人たりとも侵入を許さない。
さもなくば・・・・・
さもなくば、噛む。
お前を、噛む。
喉元に食らいつき、引き千切り、
返り血を浴びながら臓腑をかき分け、その死を咀嚼する。
哀れなお前は他人の血肉に成り果てるのだ。
それが嫌なら・・・帰れ。』
・・・・・と。この犬はオレを威嚇してやがるのだ。
フン、言ってくれるぜ。
「吠えるなよ、小犬風情が」
「わん」
また、吠える。
その意味は、こうだ。
『久しぶりに出会ったよ。
我の咆哮を聞いて、逃げ出さない男・・・
お前は何物だ』
「オレか? 決まってる。
オレはクォレルだ。何物でもねえ。
エピソードもアイデンティティもねえ。
クソ食らえだ。オレはゼロから生まれたからな」
「わん」
『十分!
全くもって喜ばしい!
我が血肉となるに相応しい存在だ!!』
ゴミ箱にあったやつです。ミヤコとネタがかぶってるのう
『絶対的孤独を突破』とかいう言い回しに、何だそりゃ、と思った。
- 「あたしのヴェル」 Scina>ポーン 03/05/10 12:12
to ポーン様
アイヤー昨日の夜にメールを開いたときにはもう衝撃でしたよォ!
まさかまさかポーン様の方からアプローチされるなんて。
思わず両手で顔を覆ってアヒャーと口走っちゃいまして。
お察しの通り、あたしはステッパーズ・ストップを毎日毎日毎日訪れて
影響を受け、育った人間です。(と言っても5ヶ月の歴史ですが。)
と、自己紹介よりも先に喜びをお伝えしたことをご容赦くださいなと。
あと昨日はあんまりにテンパってしまって、とてもお返事なんて書けそうになく、
返信遅れてしまいましたアー言い訳。
エー改めて、はじめましてです。
Unblossomedの管理人をやっとりますScinaです。
と言っても、お互いにお互いのホームページを知っていたのだから、
はじめましてってのはおかしいですかね?
おかしくないですね。
それでまた嬉しいのが、ポーン様の『ヴェル』解釈が正しいこと正しいこと。
あ、もちろん『ヴェル』はあたしの造語です。はい。
マー、要はヒッチコックが言ってた『マクガフィン』の猿マネなわけで。
しかし、やっぱ勝手に創った言葉を説明も無しに文章に組み込むってのは
無理があったみたいでして、意味を聞かれたり誤解されたりってのは
しょっちゅうでした。
でもポーン様にここまで深ーく正しく理解されてもう、それだけで歓喜モノです。
あたしは絵はともかく、テキストとサウンドに関してはちぃーとプライドを
懸けてるんで、そこんところを敬愛するひとにあんな風に誉められて、
なんてーか、アー、
溶けてしまいそうです。
ヒャアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
すいません、テキストに誇りがあるなんてどの口で言ってんだって
話ですよね。こんな奴なんです、あたし。
まだ高揚が収まってないようです。
最初にポーン様のゲームをプレイしたのは、
雑誌に収録されていたフィラデルフィア演義。
たまたまプレイして虜になったのが初期衝動で、以来、
雑誌にポーン様の新作を見つけるたびに狂喜したものです。
あたし、パソコンは結構前から曲作りのために使ってたり
してたんですが、インターネット環境がありませんで、
ようやくプロバイダと契約して出来るようになったのが去年の12月。
回線つないだら真っ先にステッパーズ・ストップのURLを打ち込みました。
生涯で初めて訪れたホームページ、そこで見た文章や掲示板やまだ見ぬ新作に
触れたときはもう、感動なんてものじゃありませんでした。
すぐに、メールを送ってみようかとも思いました。
ミヤコアーカイブに投稿しようかとも思いました。
でも、あたし、ただの一ファンとして認識されてお終い、だけじゃ
つまらないなって思ったんです。
ホームページもずっとずっと作りたいと思ってたんで、それをして、
創作物もアップして、ある程度の成果を出してから、対等に話したい。
そんな夢を抱いていたのです。夢を抱くからには、それをします。
実現につながらない夢など見たくもないので。
ってわけでコッソリコッソリと技術を磨いていたんです。
いつかきっと、満を持してこちらからアプローチをかけようと。
そしたら、既にポーン様に見られてて評価までされていた! という
予想外も甚だしい展開に、このよーな有り様で取り乱してしまったと。
ほんとはポーン『さん』から始める予定だったのですが今はまだ、『様』です。
エェ、『今はまだ』です。
イヤそんな風に呼ばれたところで別段ポーン様には面白くはないでしょうし
そんなに畏まってくれるな、という声も聞こえてきそうですが、
マァこれはあたしにとっての儀式みたいなものです。
自分の創作物に本当にプライドが持てるようになったとき、
その時に改めて『さん』で呼ばせてもらいたいなと。
そういう遊び、と思って。
お付き合いいただければと。
ナーンカ長々と、好き勝手書いた見苦しいテキストになってしまいましたね。
しかもあたしのことばっか喋っちゃって、すみません。
でも、ポーン様の作品への想いですとか、lainやなるたるの話ですとか、
まだまだお話ししたいことは沢山あるんです。
また改めて、ご迷惑でなければ、この拙い文にお付き合いください。
よろしくお願いします。
by Scina
↑の文は、今、僕が書いたものです・・・なんつうか、ごめんなさい。
何せあのポーン様にメールを書くなんて初めてだったので、緊張しました。